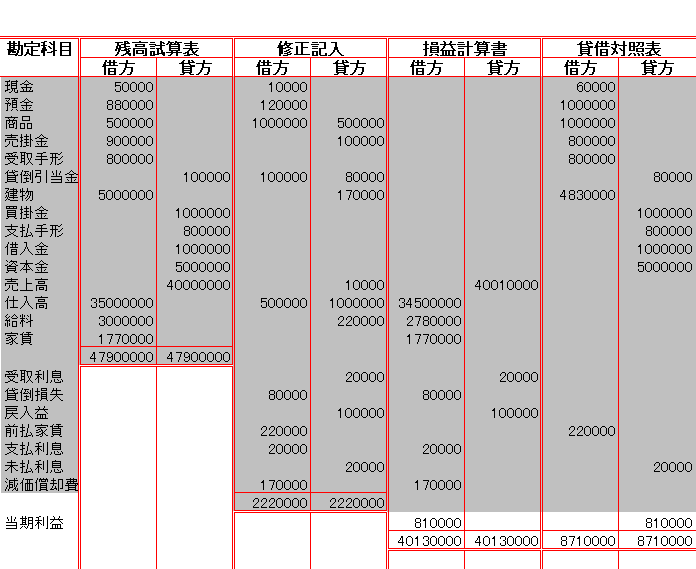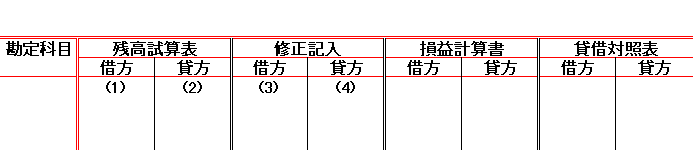
8桁精算表にかんする説明と練習問題
8桁精算表の記入方法
8桁精算表としては、下に示すような勘定科目名記入欄のほかに、残高試算表、修正記入欄、損益計算書、貸借対照表についてそれぞれ借方・貸方の金額記入欄が合計8欄あるものを想定しています。
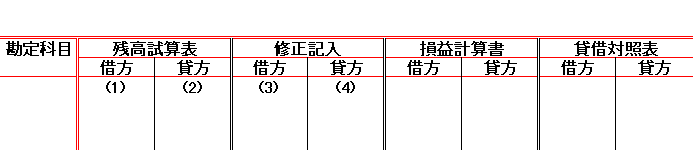
手順1
総勘定元帳の科目名を精算表の勘定科目欄に転記します。
残高試算表には、総勘定元帳の決算整理直前の残高を転記します。
記入が終了したら、必ず借方合計と貸方合計とを計算し、金額が一致していることを確認します。金額が一致していれば、その合計金額を残高試算表の借方・貸方の下段を横線で締め切ります。そして横線の直後に合計額を記入し、二重線で締め切ります。
手順2
修正記入には、決算予備手続きなどで判明した期末整理事項についておこなった仕訳にしたがい、手順1で記入した勘定科目欄に科目名がなければ追加し、金額を記入します。
記入が終了したら、必ず借方合計と貸方合計とを計算し、金額が一致していることを確認します。金額が一致していれば、その合計金額を修正記入の借方・貸方の下段を横線で締め切ります。そして横線の直後に合計額を記入し、二重線で締め切ります。
手順3
損益計算書、貸借対照表については、各勘定科目の属する区分(収益・費用・資産・負債・資本)に応じて、残高試算表と修正記入の借方・貸方の金額をもとに計算して、その結果を記入します。
費用科目=+(1)−(2)+(3)−(4)
収益科目=−(1)+(2)−(3)+(4)
資産科目=+(1)−(2)+(3)−(4)
負債科目=−(1)+(2)−(3)+(4)
資本科目=−(1)+(2)−(3)+(4)
なお、資産勘定であっても、貸倒引当金などの評価性引当金や減価償却累計額については
=−(1)+(2)−(3)+(4)
とします。
手順1および手順2で借方合計および貸方合計が一致していることを前提に話を進めます。
記入が終了したら、必ず損益計算書と貸借対照表とについて、それぞれ借方合計と貸方合計とを求め、借方合計−貸方合計をもとめます。手順3が正常に実施されていれば、差額の金額は、お互いが正または負であるものの必ず一致します。
一致していない場合
一致しない場合は、手順に誤りがあるので順を追って検査し原因を明らかにし訂正します。
一致している場合
・損益計算書で借方合計(費用の合計)−貸方合計(収益の合計)が正(プラス)のとき
収益よりも費用が多いのですから、当期損失となります。
貸借対照表では借方合計(資産の合計)−貸方合計(負債・資本合計)は負となります。
会社が調達した資金(負債・資本合計)が使途(資産の合計)で目減りしたのですから当期損失となります。
損益計算書および貸借対照表のそれぞれの借方合計ないし貸方合計の金額の少ないほうに差額金額を記入し、科目欄に「当期損失」と記入します。借方欄および貸方欄に横線をひき、借方合計、貸方合計を記入し、二重線で締め切ります。
費用より収益が多いのですから、当期利益となります。
貸借対照表では借方合計(資産の合計)−貸方合計(負債・資本合計)は正となります。
会社が調達した資金(負債・資本合計)が使途(資産の合計)で増加したのですから当期利益となります
損益計算書および貸借対照表のそれぞれの借方合計ないし貸方合計の金額の少ないほうに差額金額を記入し、科目欄に「当期利益」と記入します。借方欄および貸方欄に横線をひき、借方合計、貸方合計を記入し、二重線で締め切ります。
例 題
あすなろ商事の決算にあたり8桁精算表を作成することになりました。総勘定元帳残高をつぎにしめします。
| 現 金 |
50,000
|
預 金 |
880,000
|
商 品 |
500,000
|
| 売 掛 金 |
900,000
|
受 取 手形 |
800,000
|
貸倒引当金 |
100,000
|
| 建 物 |
5,000,000
|
買 掛 金 |
1,000,000
|
支 払 手形 |
800,000
|
| 借 入 金 |
1,000,000
|
資 本 金 |
5,000,000
|
売 上 高 |
40,000,000
|
| 仕 入 高 |
35,000,000
|
給 料 |
3,000,000
|
家 賃 |
1,770,000
|
手順1にしたがい残高試算表欄に科目名および金額を転記します。
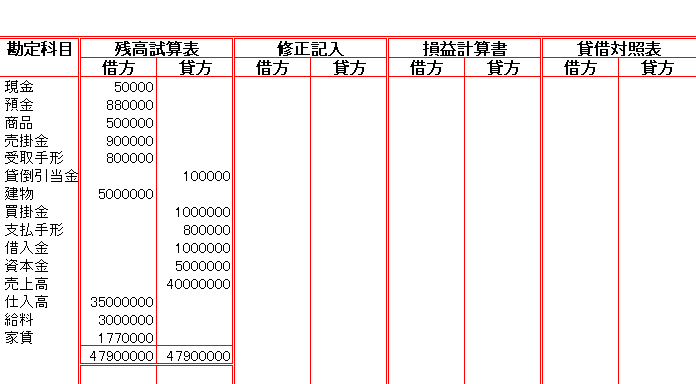
ついで決算整理事項にかかる仕訳をおこない、修正記入欄に記入します。
決算整理事項
1.当社の期末商品在庫は100万円である。
2.預金通帳残高と元帳の預金残高が一致しないので調査したところ、大谷商店からの売掛金10万円の振込み入金があったが未処理であることが判明した。
3.同じく、預金利息2万円が振り込まれていたが未処理であった。
4.当社は営業債権(売掛金・受取手形)の5%の貸倒見込みをおこない貸倒引当金を設定している。なお当社は差額補充法を採用していない。
5.家賃のうち22万円は、翌期分の前払分であることが判明した。
6.借入金利息2万円が未払いである。
7.建物の減価償却費は17万円である。なお当社は直接法を採用している。
8.現金の実際残高は6万円であった。原因を調べたところ現金売上の記帳もれであることが判明した。
以上。
修正仕訳の実施
1.当社の期末商品在庫は100万円である。
総勘定元帳上の商品勘定の残高は50万円である。期末の商品は100万円あるので、これを100万円としなければならない。また当期に販売しようとした商品は、当期に仕入れた3500万円に前期に売れ残った商品50万円を合計したものである。しかし期末に100万円売れ残ったのであるから、実際に当期に販売したのは3450万円となる。これを売上原価という。この関係を仕訳でしめす。
(借方)仕入 500,000 (貸方)商品 500,000
この仕訳により、前期に売れ残った商品を販売用の商品を管理する勘定科目である仕入勘定に振り替えています。
(借方)商品 1,000,000 (貸方)仕入 1,000,000
この仕訳により、販売用の商品を管理する仕入勘定から、期末に売れ残った商品を商品勘定に振り替えています。
結果として、商品勘定では50万円−50万円+100万円の計算が行われ、商品勘定の残高は100万円となります。
また仕入勘定では3500万円+50万円−100万円の計算が行われ、仕入勘定の残高は3450万円となります。
2.預金通帳残高と元帳の預金残高が一致しないので調査したところ、大谷商店からの売掛金10万円の振込み入金があったが未処理であることが判明した。
預金に売掛金10万円が振り込まれていたのであるから、もともと次の仕訳をすべきであったのが未処理であっただけである。
(借方)預金 100,000 (貸方)売掛金 100,000
3.同じく、預金利息2万円が振り込まれていたが未処理であった。
預金利息として2万円を受け取っていたのが仕訳されていないのであるから
(借方)預金 20,000 (貸方)受取利息 20,000
4.当社は営業債権(売掛金・受取手形)の5%の貸倒見込みをおこない貸倒引当金を設定している。なお当社は差額補充法を採用していない。
売掛金の残高は2で変更されていることに注意する
売掛金と受取手形の合計学は 900,000−100,000+800,000=1,600,000 となる
1,600,000の5%を貸倒引当金の額とするのであるから
1,600,000×0.05=80,000 が期末貸倒引当金の額となる
仕訳の方法として、差額補充法を用いないのであるから、
前期繰越額の取り消しをする仕訳
(借方)貸倒引当金 100,000 (貸方)貸倒引当金戻入益 100,000と
*精算表の科目名は、記入枠の制限のため「戻入益」と省略表記している
新規に設定をおこなう仕訳を実施する必要がある。
(借方)貸倒損失 80,000 (貸方)貸倒引当金 80,000
5.家賃のうち22万円は、翌期分の前払分であることが判明した。
いわゆる費用の繰り延べの問題である。家賃支払いとして経費処理した22万円が、この会計期間の費用とならないのであるから、前払の費用として資産計上する。
(借方)前払家賃 220,000 (貸方)家賃 220,000
6.借入金利息2万円が未払いである。
いわゆる費用の見越しの問題である。本来支払うべき利息を会計期間終了時までに支払っていないのであるから、未払いの費用として債務計上する。
(借方)支払利息 20,000 (貸方)未払利息 20,000
7.建物の減価償却費は17万円である。なお当社は直接法を採用している。
減価償却の仕訳方法には、間接法と直接法とがあることに留意すること。
(借方)減価償却費 170,000 (貸方)建物 170,000
8.現金の実際残高は6万円であった。原因を調べたところ現金売上の記帳もれであることが判明した。
現金の元帳残高は5万円であるが、実際は6万円あるということだから、1万円元帳の残高が不足しているということである。その原因が現金売上の記帳もれであるということなので、もともと次の仕訳をするべきであった。
(借方)現金 10,000 (貸方)売上高 10,000
以上で修正仕訳が完了しました。そこで上記仕訳により修正記入欄の適切な行に金額を記入するとともに、勘定科目欄に未記入の科目名は追加記入します。検算のため修正記入欄の借方合計と貸方合計とを求め、その金額が一致することを確認します。金額が一致すれば、求めた合計額を下図のように記入し、二重線で締め切ります。
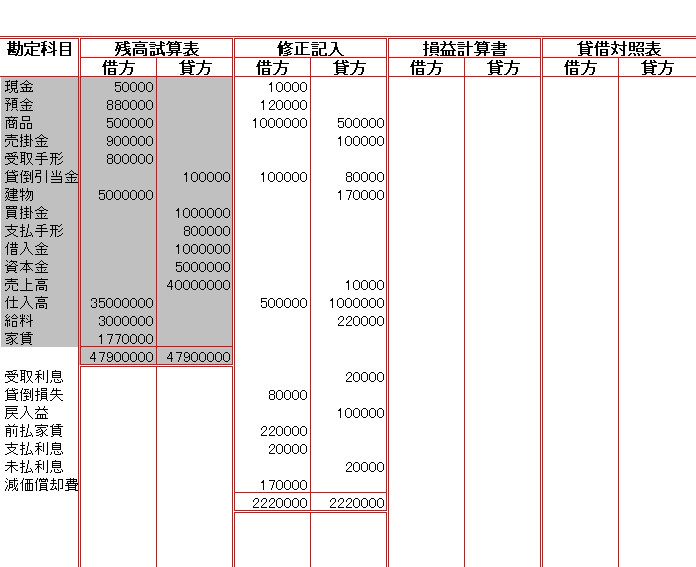
修正記入が完了したら、勘定科目が収益・費用科目に属する科目については損益計算書の借方ないし貸方に計算結果を記入します。それ以外の勘定科目、資産・負債・資本科目に属する科目については貸借対照表の借方ないし貸方に計算結果を記入します。
勘定科目欄に記入された科目のうち
収益科目は:売上高、受取利息、貸倒引当金戻入益
費用科目は:仕入高、給料、家賃、貸倒損失、支払利息、減価償却費
資産科目は:現金、預金、商品、売掛金、受取手形、貸倒引当金、建物、前払家賃
負債勘定は:買掛金、支払手形、借入金、未払利息
資本勘定は:資本金
となります。手順3にしたがいそれぞれの借方・貸方の記入を実施します。
記入が終了したら、損益計算書および貸借対照表の借方・貸方の合計を求めます。下図では、求めたそれぞれの計を青色で表示しています。そして損益計算書の借方と貸方との差額と、貸借対照表の借方と貸方との差額とが同額となることを確認します。
損益計算書の差額=39,320,000−40,130,000=−810,000
貸借対照表の差額=8,710,000−7,900,000=810,000
差額が符号を異にして一致していますから、一応は正しい処理がされています。
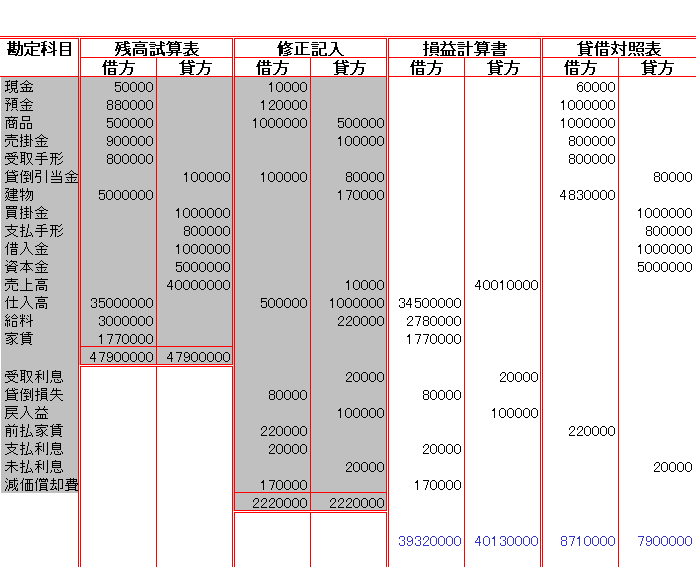
次に差額が利益か損失かを判定します。費用より収益の額が多いので利益が生じたことがわかります。そこで勘定科目欄に「当期利益」と科目名を記入します。そして損益計算書においては合計額が少ない借方に、求めた差額810,000を記入します。また貸借対照表においても合計額の少ない貸方に、求めた差額810,000を記入します。
利益額を記入したら横線をひき、その下に損益計算書の借方では利益を含めた合計額を、貸方では先ほど求めた合計額を記入し、二重線で締め切ります。貸借対照表においても同様にして処理をします。結果は下図のようになります。