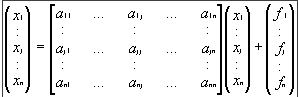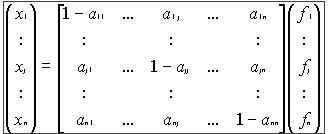|
1 はじめに
名古屋工業技術研究所(略称「名工研」、旧称は名古屋工業技術試験所で略称「名工試」)瀬戸分室は、日本で唯一の国立陶磁器試験所として瀬戸を中心とする陶磁器業界の発展に深く関わってきた。瀬戸の陶磁器関係者や近隣地域の住民などからは、愛着と親しみをもって
“めいこうし”(名工試)と呼ばれてきた。“陶都”瀬戸のシンボルであったともいえる。1993年に名称変更され、現在では“めいこうけん”と呼ばれている。 この「名工研」瀬戸分室が、2001~2007年でもって「名工研」名古屋本所に移転統合されることになっている。瀬戸分室は、瀬戸の陶磁器産業の発展・衰退とほとんど軌を一にしてきた。とくに、1970年代に始まった陶磁器部門の研究体制の困難化・縮小化は、1986年の国立試験所の見直しで決定的となり、「名工試」の組織ならびに研究テーマから
“陶磁器”の名前が消えたのである。本所への移転統合は、こうした流れの最終作業といえよう。
かつては瀬戸の陶磁器産業における技術の中核をなし瀬戸のシンボルの一つであった「名工研」瀬戸分室の移転統合計画は、市民の間ではあまり知られていない。陶磁器業界の斜陽化とともに後景に退き、静かに消え去ろうとしているのである。しかしながら、それは、瀬戸の産業と街づくりにとって、きわめて重要な問題を投げかけていると思われる。瀬戸の産業と技術、そして街づくりの歴史が深く刻み込まれているからである。
それでは一体、瀬戸の地場産業と街づくりにおいて、「名工研」瀬戸分室は歴史的にどのような役割を担ってきたのであろうか。そして、それが移転する(陶磁器部門は実質的になくなる)ことがいかなる問題が投げかけているのか。そこに所蔵されている陶磁器関連の膨大な釉薬試料や収集品、各種設備は、どうなるのだろうか。さらに瀬戸市の玄関口に位置する同室の建物と膨大な土地などは、移転後にどのように利用されるべきなのか。
小論は、上記のテーマを中心にして考察したものである。これらは、21世紀に開かれた芸術文化都市としての瀬戸の街づくりを考えていくうえでも、試金石になると思われる。筆者がこの問題に関心を持ったのは、「瀬戸の産業と文化を考える」会において1998年春から夏にかけて行った数回にわたる議論に触発されてのことである。そこでの議論をふまえ、また各種ヒアリングや現場見学によって検証し、筆者なりの視点でもってまとめたのが小論である。
この間に、瀬戸市役所の商工観光課より経過説明を受け(1998年4月14日)、また5月19日には研究会メンバー10人で「名工研」瀬戸分室に伺い見学とヒアリングをさせていただいた。同室からは、芝崎靖雄・セラミックス応用部長、黒川利一・同部主任研究官、杉山豊彦・同部環境セラミックス研究室の3氏が出席された。さらに、7月7日には筆者が瀬戸分室に再度伺い、黒川氏から技術的な内容について再ヒアリングを行うとともに、新たに植田哲哉氏からもヒアリングさせていただいた。植田氏は1998年3月末に名工研を定年退職されたが、陶磁器部門の試験研究を中心的に担ってこられた方である。
以上にみるような経緯での議論と見学・ヒアリング、それらは筆者にとって瀬戸の産業と街づくりを考えるうえでの実に貴重な体験でもあった。このテーマには、また多くの重要な問題と可能性が潜んでいるのではないか思われる。これらを、「名工研」や陶磁器業界、行政など関係者だけの関心事にとどめておくことは適切ではなかろう。行政などに提起するとともに、広く市民にも開陳し、地場産業と街づくりのあり方について、議論をすべきではなかろうか。本稿は、こうした視点から提示するものである。
まず最初に、「名工研」瀬戸分室の歴史的歩みを、資料などに基づき概観する。次に、瀬戸分室の見学・ヒアリングをふまえて、瀬戸分室の各種資産、ならびに地域との歴史的な関わりについて分析し評価している。最後は、瀬戸分室の移転問題ならびに各種資産の活用のあり方についてささやかな提言を行う。
2 名古屋工業技術研究所(「名工研」)瀬戸分室の歴史的歩み
(1)「名工研」の沿革と機構の変遷
名古屋工業技術研究所(「名工研」)の瀬戸分室は、その前史も含めると100年余の歴史を持つ。陶磁器に関わる国立試験研究所としては日本で唯一の機関であり、陶磁器に関わる試作・試験研究の多岐にわたる膨大な各種試料が保存されている。
①前史
「名工研」瀬戸分室は、1896年(明治29年)にわが国唯一の陶磁器試験場として設立された京都市立陶磁器試験所時代(1902年、「試験場」に改称)からの歴史的な遺産を継承してきた。その後、京都市立陶磁器試験場が国に移管され、1919年(大正8年)に設置されたのが農商務省直轄の陶磁器試験所である。
②名古屋工業技術試験所(「名工試」)の発足
戦後になって、陶磁器試験所は名古屋に移転集約される。それが、「名工試」と呼ばれてきた名古屋工業技術試験所である。「名工試」は、1952年に通産商工業技術庁(同年、工業技術院に改組)の総合試験所として設立された。工業技術庁直轄の陶磁器試験所、ならびに機械試験所名古屋支所、東京工業試験所名古屋支所、東京工業試験所本所の一部が統合されたものである。322名の定数で、陶磁器試験所の京都本所および瀬戸の東海支所から128名が移った。
敷地と施設などは、上記の両名古屋支所のそれを引き継いで、本所とした。敷地面積は51,635㎡で、当時は愛知県所有地であったが、後年、国に移管している。陶磁器試験所京都本所の設備・資材の大半は、名古屋本所に移設された。東海支所は名工試瀬戸分室となる。なお工業技術庁は、名工試発足後の同年8月に、工業技術院に改組されている。
③(名工試~名工研)陶磁器部門における研究組織の変遷
Ⅰ「名工試」(~「名工研」)瀬戸分室の源流
「名工試」瀬戸分室の直接の分身は、1932年(昭和7年)に開設された瀬戸市立窯業試験所である。翌年(1933年)国に移管され、陶磁器試験所の瀬戸試験場になる。瀬戸試験場は、1952年に陶磁器試験所東海支所に改称され、さらに同年、名古屋工業技術試験所が設立されると、東海支所は「名工試」瀬戸分室へと改称された。「名工試」は、1993年に名古屋工業技術研究所(「名工研」)へと改称される伴い、「名工研」瀬戸分室となり現在に至っている。
Ⅱ 磁器部門は所内最大の部門
名工試(1952年)発足に伴い、6研究部制になる。第1部は機械試験所名古屋支所、第3部に東京工業試験所名古屋支所、第4部が東京工業試験所、そして第5部と第6部は陶磁器試験所の従来からの研究分野が、それぞれ引き継がれた。
翌年(1953年)には新研究体制への移行に伴い、陶磁器部門は第6部に集約された。第6部は、3課と7研究室からなる所内で最大の部門となる。
Ⅲ 瀬戸分室の充実と試作重視
さらに、1958年の機構改革において第6部は3つの課に再編され、瀬戸分室の充実が図られた。すなわち、瀬戸分室の意匠と制作を分離し、それぞれ課として独立させ、輸出の振興と業界の指導を強力に推進する体制が敷かれたのである。1958年の機構改革で一段落した第6部の研究体制は、1975年まで17年間続く。
1970年代頃までは、陶磁器試験所の流れを引き継いで、試作に重点が置かれていた。輸出振興の立場から輸出用陶磁器が多く試作され、米国で開催される見本市をはじめ、国内の展示会などへ積極的に出品される。
Ⅳ 試作重視の困難化
しかし、1970年代になると、名人と呼ばれた職人気質の職員が、高齢化し退職する。また、技能職員の技能が正当に評価されない賃金政策の下で、優秀な職員の採用が著しく困難になる。
その結果、試作体制は徐々に縮小していく。さらに、重化学工業の発展(貿易収支の黒字化)にともない、それまでの輸出振興を目的とした研究テーマも消えた。
1976年に、瀬戸分室の研究本館が完成する。これを機に、17年間続いた第6部の組織は、改編された。瀬戸分室の意匠と試作が一つの課(第3課)に集約されるとともに、本所の試験研究機能の一部が瀬戸に移され、本所はより基礎的な研究機能の性格が強まる。
Ⅴ「陶磁器」「試験所」の名前が消える
1986年には、技術革新の急速な進展を背景に、国立試験所の見直しが行われた。「名工試」においても、長期的な基礎及び応用研究分野における独創的な研究などに向けて、研究テーマと人員構成の見直しがなされた。
第6部は、セラミックス応用部に改編された。1986年はまさに、「名工試」の組織から「陶磁器」という文字が消えた年となったのである。また研究テーマからも、陶磁器が消えた年となる。
1993年に名工試は、名古屋工業技術研究所(「名工研」)へと改称された。「試験所」という看板が消え、「研究所」に塗り変わったのである。同時に課制は研究室制になり、セラミックス応用部は4研究室に再編され現在に至っている。
④「名工研」瀬戸分室の現況と移転計画
「名工研」瀬戸分室は、名鉄・尾張瀬戸駅の南側に位置し、文化センターや瀬戸窯業高校と近接するなど、瀬戸市の玄関口・尾張瀬戸駅に近い要衝の地にある。敷地面積は12,350㎡(約3,700坪)と広く、多くの緑に囲まれている。
1976年完成の鉄筋建ての研究本館は、外見上はしっかりしており、一定の補強を施せば今後の使用には十分に耐えうるとみられる。敷地内に宿舎・寮もあるが、現在では空き家になっている。
釉薬の調合試験室には、1975年にドイツより技術導入した「石川式攪拌擂潰機」が備え付けられており、アルミナ、シリカの添加量を調合する。擂潰機は特許の塊のようなものであり、瀬戸分室に数台設置されている5機連続式は、当室の工夫が加味されているという。
ガス窯のうち、3㎡窯はすでに処分されているが、6㎡、1㎡のガス窯がある。また、1,350℃まで上げられる10kWの電気窯もある。以前は、試作品も作っていた。
「名工研」瀬戸分室の移転統合計画は、1980年の行政監察に端を発している。すでに職員は、1998年4月時点で3.5人に減っており、研修生の受け入れについても98年は1人にとどまっている。移転作業は、2001年(平成13年)にスタートし、2007年(平成19年)までには完全に引き上げることになっている。
(2)試験研究活動の歩み
陶磁器試験所の創設当初は、建築用装飾陶磁器や輸出向け洋食機などの試験研究、青磁をはじめ釉薬・顔料に関する試験、白雲陶器など新しい素地の開発、コージェライトなど新しい先取的な研究等、広い視野に立ったテーマが研究に取り上げられた。
「名工試」発足後は、原料、素地、釉・顔料などの基礎的研究や製造技術、デザインなどの応用研究、さらにはファイン・セラミックスの分野でも人工粘土やバイオ・セラミックスなどの先取的テーマが取り上げられ、研究が続けられてきた。
このほかにも、地方の試験研究機関の職員の研修や研究発表会、企業の技術指導や共同研究、さらには発展途上国との国際協力研究および海外研修生の受け入れなども行われてきた。
① 原料・素地の研究
原料の精製技術や品質試験などの基礎研究が進められたが、その一方で、新しい素地の研究についても設立当初からの課題であった。
当時(昭和初期)、欧米の陶磁器市場では形質の石灰質陶器(マジョリカ)が流行していた。試験所は、これに対抗しうる新しい輸出用陶磁器素地の開発を進める。こうした中から、「白雲陶器」と呼ばれる軽量かつ低火度の陶器が開発された。これは、戦後、瀬戸の輸出用ノベルティの主力製品になるのである。
なお、白雲陶器の開発にあたっては、海外の収集品が大きな威力を発揮した。武田五一(京大教授、建築家)が1931年(昭和6年)に欧米に出張する際に、ヨーロッパで流行している実用的な陶磁器製品見本の収集を委託する。彼が収集したドイツの陶磁器102点を参考にして、素地および釉薬の開発が行われた。ヨーロッパの白いマジョリカ風素地の開発研究は、1933年に実を結び、従来の日本にはなかった全く新しいタイプの低火度焼成用陶器が開発された。白雲石(ドロマイト)を使用していることから白雲陶器と命名されたのである。
このほか、骨灰の替わりに燐鉱石を用いたボーンチャイナや白雲石を融剤とするアイボリー磁器の開発が行われた。
さらに戦後は合成透輝石を用いた新しい型の低火度磁器としての「フリット磁器」が発表されるなど、いくつかの新しい素地の研究開発が続けられてきた。
② 釉・顔料・絵具の研究
戦前には、天龍寺青磁や砧青磁釉薬の研究、硬質磁器用呉須の発色試験、灰釉、鉄釉、均窯釉など、伝統的な釉についての研究に優れた実績が多い。これらは「試験所のお家芸」にもなっている。
とくに、試験所創製の高火度用顔料として広く業界に普及した「陶試紅」や、英国製のダルトン赤を模して鮮やかな赤色を発色させる「陶試辰砂」の研究は、試験所独自の業績として高い評価を得ている。
戦後は、希元素の顔料への応用化研究として、「セレン赤」、「トルコ青」や「プラセオジウム黄」など新しい顔料が研究開発された。
その他、結晶釉、鉄赤釉の研究など、研究成果は枚挙にいとまがないほどである。現在、当研究所にはこれらの研究で調製された試験見本の数千点が備えられている。
③ デザインの研究と試作
試験所が創設された当時は、建築ブームにあって、タイルや陶板、装飾瓦などの需要が増加した。試験所における研究の中心も、こうした建築用装飾陶磁器に向けられる。それらのさまざまな試作品には質的には優れたものが多く、海外の展覧会に出品して賞を獲得したものもある。
その後、輸出用陶磁器振興のための意匠図案の研究と試作が、重視されるようになる。とくに、日本の伝統的デザインの洋食器への応用研究が注目され、染錦など多様な伝統的技法を駆使した試作品が発表された。
白雲陶器が開発されると、米国市場をターゲットにした本格的なデザイン研究が始まり、ノベルティと呼ばれる各種の室内用品が試作された。また、ノベルティの輸出振興のデザイン研究として、「彫刻の工芸化研究」が1932年から始まった。芸術的価値の高い動物置物などが制作され、優れた評価を獲得する。
戦後は、輸出向け先導商品の開発を中心に、新しい形のノベルティ、機能性重視の飲食器、さらには未利用資源の有効活用によるせっ器製品の試作など、数多くの試みがなされてきた。
④ 新素材の研究
新素材への取り組みは、設立間もない頃から開始している。すなわち、低膨張性耐熱素地についての研究である。当時、まだ知られていなかったコージェライト素地の特性を解明したものとして、画期的
な成果をあげた。その後、コージェライトは、日用煮沸容器や戦時中の金属製品の代用品としての使用などで、注目を集めた。
また、戦時中は、高周波絶縁材料として、ステアタイトに関する研究が重点的に行われた。この研究は戦後に引き継がれ、新たに透輝石磁器、フォルステライト磁器、マグネシア磁器、アルミナ磁器などが加えられ、順次研究されていった。
最近では、天然原料に変わる人工粘土の合成や人工歯骨などのバイオセラミックス分野での研究などに著しい成果を収めている。
⑤ 海外の収集品
現在、当所に所蔵されている海外の収集品は、昭和初期(1928年)に輸出向け陶磁器のデザイン研究や試作のための材料として集められたものなどから成っている。当時、欧米の生活用式や商品知識などの情報に乏しく、収集された参考品は研究上で大いに役立ったものと考えられる。
収集のやり方は、職員が海外へ出張した折に現地で購入したもの、欧州の製陶所との間の作品交換展で得られたもの、あるいは国内で購入した製品など、様々である。
海外収集品の収集活動は、3期に分けられる。第1期は、京都市立陶磁器試験所時代―1898~99年(明治31~32年)―の収集品である。明治31年に藤江永孝所長が南清を視察した際に江蘇省の常州府で朱泥・白泥を、江西省の景徳鎮で磁器製品などを収集し、またその翌年にドイツなどに滞在した際に多数のヨーロッパ製品を収集し、持ち帰ったものである。この他、入手経路は不明であるが、中国、朝鮮、日本の古陶器が相当数ある。
第2期目は、陶磁器試験所時代の収集品である。1931年(昭和6年)に武田五一に依頼してベルリンとデュッセルドルフで購入したドイツで流行していた実用陶磁器102点、および1940年(昭和15年)に水町和三郎が南北アメリカの工芸事情を視察した際に収集した欧米の陶磁器製品80点である。このうちの約70点が現在も収蔵されている。
第3期目は、「名工試」時代である。1959~61年の日仏作品交換展に際しセーブル製陶所から送られたディナーセットと花瓶など、洋食器の研究のための日本のデパートで購入したヨーロッパ製ディナーセットなどがある。
収集は輸出振興という目的に沿って行われ、1970年代前半まで続いた。こうして収集された参考品のうち、約2,000点が収蔵されている。その中には、中国や朝鮮の美術的評価の高いものも含まれている。しかし、その大半は19世紀後半から20世紀にかけての実用的な飲食器や装飾用など、日用品を中心に集められている点に特徴がある。現在、日本ではこうした所は他になく、産業博物館的な価値を持った貴重な研究資料とみなすことができる。
⑥ 試作品
当所には、また試作品の約1500点が所蔵されている。これらの試作品には、陶磁器試験所時代から名工試時代、現在に至る80年近くにわたる研究成果が凝縮している。
これらの試作品は、当所で研究開発された各種の成果、すなわち各種青磁器、天目釉、釣窯釉、辰砂釉、陶試紅、合成呉須、新染付、ボンチャイナ、白雲陶器、昭和陶器、透光性磁器、アイボリー磁器など、を応用して試作されたものである。
また、大量に製作された建築陶器、装飾品、洋食器などの一部も保管されている。
⑦ 伝習生・研修生制度
伝習生制度は、1928年(昭和3年)に制定されたものである。全国の陶磁器業者の子弟または将来陶磁器工場あるいは陶芸を志すものを対象とし、応募資格は陶磁器の製作に経験のある男子で、団体または工場主の推薦が必要であった。定員は15名で、費用は無料である。伝習開始時期は4月、10月、期間は5ヶ月(1年間の継続が可能)であり、毎年官報に公告された。戦前だけで37回の修了生を送り出し、その延べ人数は436名にのぼる。人間国宝(楠部弥一、近藤悠三、塚本快示)など無形文化財保持者、日展、伝統工芸展などの審査員、あるいは業界のリーダーなど、多くの有為な人材を輩出している。
「名工試」時代には研修生制度に改称され、1952年以降において400数十名にのぼる修了生を送り出してきた。
⑧ 海外研修員受け入れと技術協力
発展途上国に対する政府ベースの技術協力は、コロンボ・プランへの参加を機に1954年に開始された。同年、アジア協会を設立し、加盟アジア地域を対象にした研修員の受け入れが始まる。現在、その事業は国際協力事業団(JICA)に引き継がれている。
「名工試」第6部は、すでに設立直後の1952年にフィリピンから所内最初の海外研修生を受け入れている。1953年にはインドから中南米、アフリカ、中近東へと拡大する。これまでに受け入れた研修員は、延べ50名以上、受入国は50カ国を超える。
研修内容は、陶磁器の初歩的な製造技術が中心であったが、途上国における窯業技術の向上に伴い、高度かつ実践的な内容の研修カリキュラムに変えてきた。研修員は帰国後、各国の窯業分野において積極的な役割を果たし、大学教授や企業経営者になっているものも多い。
3 「名工研」瀬戸分室の各種資産、地域との関わりをどう評価するか
(1)瀬戸分室の技術的資産とその保存作業
① 収集品の展示室
収集品は国内外合わせて3,000点あり、中国の宗や明、朝鮮の高麗、有田、瀬戸焼、イギリスのダルトン、ウェジウッド等々多岐にわたる。
中国宗代(14世紀)の磁州窯、フランスのセーブル・ブルー、セーブルのせっ器(鹿や置物)、当所で開発された白雲陶器、仁阿弥道八作の三つ足付き瓢型浅鉢(19世紀)などもある。二和製陶寄贈の
「カタログ」は、昭和10年かその少し前(193035年)の頃に瀬戸で作られていた各種製品のミニチュア版を一枚の陶板に並べた逸品で、いわば当時の瀬戸の「モノづくりマップ」である。
② 釉薬・試料(テストピース)の価値
同所が所蔵する釉薬の試料(テストピース)数は、約30~40万個にのぼる。京都の農商務省陶磁器試験所時代のものも、一部含まれている。テストピースは、作った順番ごとに保管されている。これらを記録したものは、「釉試料整理簿」と呼ばれるノートで、ノートには番号が№.1から付けられている。
テストピースとにらめっこしながら、自分のやりたいものを探す。これが、従来の利用の仕方であった。箱は、棚に積み上げられていた。重い箱を棚から取り出すという作業は、それだけでもなかなか大変である。最近では空き部屋が増えたために、箱が床の上に並べられている。
通産商工業技術院の16研究所のうち、陶磁器を扱っているのは名古屋工業技術研究所のみである。これらの釉薬試料は、他所にはないものである。数が多いだけでなく、レベルが高い。マンツーマンで試験したものが多く、ずいぶんと高レベルのものがあるとのことである。
③ テストピース類のデータベース化事業
工業技術院も、「貴重かつ豊富な財産」と認識し、年間600万円の予算を投入して、データベース化を始めている。台紙に書いてある状況を、フォーマット化して打ち込んでいく。半分は人件費が占める。98年5月現在は、アルバイトを使って打ち込み作業をしており、2,600~2,700のインプットを終えた段階にある。探したい釉薬があると、たとえばコバルトの結晶(釉名称)、ゼーゲル式、焼成温度などの検索条件をインプットして、その条件に見合った試料を、テレビ画面で画像としても観察する。こうしたことを可能にするシステム化の作業に取り組んでいる。色自体の完全な再現は難しいが、大体のカラー画像を見ることができるようになる。
現在、ソフト作りを終えた段階である。これから、どのようにして膨大なテストピース類のデータを打ち込んでいくかが課題となっている。「入力作業が大変で、国レベルでないと対処できない」という声も聞かれた。
台紙の中から、使えそうなものだけを優先的に打ち込んでいくと、スピードを上げることができる。その際、失敗作などをどう扱うか、といった問題もある。
インターネットでも近々公開するとのことである。そうなると、入力データを簡素化するなど使いやすくする必要も出てくるという。
(2)瀬戸の陶磁器業界と「名工研」陶磁器部門の歴史的関わり
「名工研」(「名工試」)陶磁器部門は、瀬戸の陶磁器業界とどのように関わってきたのか。この点に関して、2人の研究者からヒアリングする機会を持つことができた。芝崎靖雄(「名工研」セラミックス応用部長)、植田哲哉(98年3月に「名工研」を定年退職)の両氏である。当部門の試験研究を中心的に担ってこられた方々である。
2人に共通するのは、瀬戸の陶磁器業界のこれまでのあり方に対する「厳しい」評価と注文である。ここでは、芝崎氏の指摘を中心にみてみよう。
瀬戸の経営者は、儲かるときには相談に来るが、5~6年先を見るテーマではやって来ない。むしろ、10~20年先を見る経営者が求められている。同所瀬戸分室の課長、研究者が、京都セラミックスに2人引き抜かれ、そこで中心になってやっている。村田製作所にも引き抜かれている。しかし、瀬戸の経営者は、これらの人材を利用しょうとしなかった。
戦後直後の占領下での南洋陶器輸出では、つくれば儲かる状況で、石炭を使用するとさらに補助金も付いた。これが、瀬戸の経営者をダメにしたのではないかと思われる。そこで儲けた金は、将来を見据えた投資に向けられなかった。瀬戸の経営者はプライドが高く、過去の栄光にとらわれ、自分の経営能力に対する過大評価の傾向も見られる。
瀬戸の陶磁器業界には、「将来こうしたい!」というビジョンや構想、哲学が欠けており、そうした体質が行政などにも反映しているように思われる。若い頃に、人工粘土の研究に取り組んでいると、ある経営者から「もっと儲かる研究をしてくれ」といった注文をつけられたことがある。
鋳型成型における「ダルマ返し」の手法も、瀬戸において転用できず、東芝セラミックスや旭ガラスなどが持っていってしまった。宇部興産などが技術指導に来ていたが、大きな魚を逃してしまったという思いが強い。
瀬戸の良質の陶土が、かなり輸出されている。貴重な地域資源の浪費である。瀬戸は国内の他地域に粘土を出し渋ってきたので、他の産地では粘土の使用量を大幅に減らして成型できるように対応している。
景徳鎮との提携にあたって、「技術が盗まれるから提携しない」といった声もあったようである。確かに、粘土の品質は、先方の方がはるかに悪い。したがって、歩留も低くなる。しかし技術は、そうした粘土を使いこなしている先方の方がむしろ上である。
染付技術は、景徳鎮や有田の方が上である。タイなどの染付技法も、瀬戸より上とみられる。瀬戸には技術がない。1993年には瀬戸でも陶磁器産業は電子機械に逆転された。現在でも、技術に対する取り組みが弱い。東濃などには、そうした動きもみられるが、瀬戸では業界として盛り上がってこない。活性化しようというあがきもあまり見られない。
4
「名工研」瀬戸分室の移転統合問題と活用のあり方
(1)「陶都」瀬戸の歴史的使命と活用の現代的意味
「名工研」の瀬戸分室には、30~40万点に上る陶磁器関連の釉薬試料が保存されている。それは、日本のどこにもない貴重な技術的資産である。また、海外陶磁器の収集品2,000点は、京都市立陶磁器試験所の時代(19世紀末)から収集されてきたものである。日本の陶磁器試験に関わる活動の重要な資料として活用されてきたものである。さらに、同所に収蔵されている1,500点の試作品は、陶磁器試験所時代の80年近くにわたる研究成果が凝縮されている。
それらは、まさに80~100年間にわたって、日本の陶磁器試験研究をリードしてきた最前線の技術的・歴史的な活動記録と成果を網羅したものである。こうした貴重な得難い技術的資産や機能が瀬戸の地に置かれてきたことに、深い驚きと感銘を覚えずにはいられない。「陶都」と呼ばれてきた瀬戸の面影がそこにも残っているのである。
しかしながら、こうした日本の粋を集めた陶磁器関係の技術的・文化的資産と機能が当地にあることの意味を、われわれはどれだけ理解し評価してきたであろうか。誇りにし大切に活用してきたといえるであろうか。県ならびに市の行政、陶磁器業界は、本当に理解してきたのか。少なくとも、瀬戸の市民の多くは、認識できていなかったといえよう。
「名工研」瀬戸分室の移転に伴い、こうした各種資料が散逸したり流出する危機が迫っていることが明らかとなった。瀬戸市や愛知県は、こうした事態に真剣に対処しなければなるまい。むしろ、これらの技術的・文化的資産を芸術文化都市としての新しい瀬戸再生の文化資産として積極的に活用するという姿勢と方策が求められているのではなかろうか。それに、同所は、地理的にも瀬戸市の玄関口にあり、その建物や各種設備は敷地も含めて瀬戸市の環境と品格の保持のために不可欠と見られる。
そうした技術的・文化的資産は、「名工研」瀬戸分室だけではない。最盛時輸出の23%にまで落ち込んだセト・ノベルティの各社が所蔵する元型(ケース)をみても、それらを合わせると、「名工研」所蔵の釉薬試料(30~40万点)を凌駕するとみられる。しかも、それらもまた今や散逸の危機に直面しているのである。
それらは、焼き物の国ニッポンにおいて、まさに瀬戸にしかない文化的資産でもある。瀬戸独自のコアの部分をいかに継承していくのか。手をこまねいている時間は残されていない。むしろ、それらを瀬戸再生の文化資源として、活用することができないのであろうか。瀬戸に関わる行政や陶磁器業界が直面する重要な課題といえよう。
こうした課題に正面から取り組まずして、芸術文化都市への再生はありえないといえよう。万博のメイン開催都市としてのブランドも品格も期待しがたいといえる。歴史が蓄積した文化コンテンツが注目される時代を迎えようとしている今日、2005年の愛知(瀬戸)万博は、新しい“陶磁の道”に通ずるといわれるような歴史的な芸術文化都市としての再生のバネにしなくてはなるまい。それがまた、万博来訪者への“おもてなしの心”にもつながるのではなかろうか。
(2)「名工研」瀬戸分室の移転に伴う活用のあり方
① 移転統合に伴う試料・収集品の扱い方をめぐって
1980年の行政監察での指摘を受け、「名工研」瀬戸分室の移転統合が、2001年(平成12年)に着工され、2003年(平成15年)には完了する予定である。
岐阜県の商工部長名で資産受け入れの要請があった。愛知県陶磁器工業相同組合(愛陶工)より愛知県工業振興課に、「釉薬試料、収集品を瀬戸における一機能として活用したい」との要請を行う。瀬戸市としても、要望書を県に提出した。県からは、「瀬戸市の意向に沿ってもよい」との感触(回答)を得ている。
同所は、これまでの研究開発試料を産業振興に向けてのデータ・ベースにしたい、そのためにも広域に研究パートナーを求めたいとの意向を持っている。一方、岐阜県は、同所とデザイン部門での共同研究をやりたい意向を表明している。しかし、上記のような動きの中で、「名工研」は、岐阜県への関連資料の移譲について正式に断っている。愛知県としても対応を迫られており、1998年2月に知事名で同所に要望書を提出した。
② オールド・セラミックス研究とそのノウハウの去就
同所瀬戸分室が積み重ねてきたオールドセラミックスの研究は、植田哲哉氏の定年退職(1998年3月)でもって途絶えることになった。彼が半生をかけてやってきた釉薬や素材研究は、先人たちの研究蓄積も含めると、日本でも傑出しており世界的なレベルにあるといわれる。1970年代前半の頃までは、瀬戸の陶磁器業界も同所をよく活用していたが、それ以降は利用されることが少なくなっている。
植田氏は、退職時まで研究官として最後の仕事をされ、釉薬試料などをデータベース化することに最後の情熱を燃やされた。退職時は、愛知芸大などで非常勤講師として講義をされる傍ら、岐阜県の「国際陶磁器テーマパーク」プロジェクトに引き抜かれ、岐阜県と「名工研」の共同研究に携わられており、その側面から名工研に埋もれている貴重な資料の整備に取り組まれている。同氏のような貴重な人材に対して、瀬戸ならびに愛知県が正当に評価し、活躍の場を提供することができないことは、実に残念なことといわねばなるまい。
③「名工研」瀬戸分室の再利用の視点
「名工研」瀬戸分室の移転統合にどのように対処し、また瀬戸の街づくりに活かすかについては、次の3点を検討する必要がある。
(a)
瀬戸における「名工試」の役割、とくに陶磁器業界との関係とその経緯について、 どのように評価し総括することができるか。
(b)
釉薬試料、収集品・試作品、各種設備など技術的資産をどうすべきか。
(c)
土地と建物をどう利用すべきか。
とくに、(a)についての評価と総括が、何よりも大切である。そして、それをふまえて、(b)が検討される必要がある。(c)についても、(a)を抜きに語ることはできまい。
(b)(c)のあり方については、活用の叩き台を作り、(a)をふまえて、わかりやすいストーリーにまとめ、関係者や市民に提起し議論をオープンにすることが求められる。本報告のねらいも、そこに向けられているといえよう。
④ 同所の技術的・文化財的評価と活用
同所は、その歴史的・文化的な位置からみて、瀬戸市の奥座敷的存在とみることができる。1976年に建造された同所の研究本館には、古いドレン(土練)機など貴重な設備もあるが、廃棄処分される予定である。研究本館を倉庫にしたいといったような意向もあり、邪魔になるからである。最盛期には、約20名の研修生がアジア・アフリカなどから派遣されてきていた。
愛知県では、「名工研」瀬戸分室はオールドセラミックス分野を主とするデータ・研究開発指向で、瀬戸窯業技術センターは一般企業を対象とするもの、といった役割分担で位置づけてきたという。
瀬戸市は、同所の持つハードとソフトをどう活用したいのかを明確にする必要がある。その産業・技術的な価値だけでなく、文化財的な価値についても評価し、瀬戸市の芸術文化都市としての品格を維持し高めるような利用のあり方を考える必要がある。
資料的価値としても高い釉薬試料や収集品、また今後も利用できる建物や各種設備、そして同所の立地環境などを活かした再利用のあり方が問われている。
(3)瀬戸分室の技術的・文化的資産を瀬戸の街づくりに活かす提言
同所の建物は、1976年の建造ゆえに耐震設計が不十分とみられる。再利用にあたっては、相当な補強が必要かもしれない。「同所で若い頃に研修し、釉薬のサンプルなどを作ったこともあって愛着がある」という経営者もいる。
跡地を公園にする、福祉センターにする、一般図書館にするといった案も考えられるが、陶磁器関係の学術研究センターとして利用してはどうかという声に耳を傾ける必要がある。瀬戸の陶磁器関係と関わってきた長い歴史と愛着が、市民のなかにみられるからである。
そこで、今後の議論のたたき台として、陶磁器に関わるユニークかつ分厚い資産をいかに活用するか、歴史的な芸術文化都市としての瀬戸の再生にいかに活かすかという視点から、一つの提案をしてみたい。
たとえば、陶磁器関係の大学院をつくり、そこで学び研究するとともに、瀬戸の地で独立してもやれるような地域と産業のネットワークづくりのセンターにしていくといった案も考えられる。文科系の歴史的・経済的な陶磁器産業・文化の研究機能も有する総合的なセンターとして活かすことができないだろうか。このためには、愛知県と瀬戸市の物心両面にわたる支援とともに、愛知県立芸術大学を中心として名古屋学院大学、愛知工業大学など近隣大学とも連携したアプローチが望まれる。
現在は、新素材研究とオールドセラミックスの研究が二分化されてしまっている。新素材の研究成果を、陶磁器づくりのレベルにいかに応用し利用するかといったアプローチの研究が抜けている。それゆえ、同所が取り組んできたオールドセラミックスの伝統をふまえたあり方が望まれる。
陶磁器関連の釉薬試料や収集品、試作品などを活かした陶磁器試験研究資料館、あるいは陶磁器専門図書館などの構想についても検討してみてはどうであろうか。
なお、県レベルにおいて、「名工研」の管掌部門は商工部であるが、大学関係の管掌部門は総務部の私学振興室である。一方、市レベルでは商工部商工観光課の管轄となっている。県・市レベルにおいて、どこを窓口にするのが妥当なのかについても、留意する必要がある。
おわりに
1世紀にわたる歴史を有する「名工研」瀬戸分室の技術的資産やノウハウ、瀬戸の陶磁器産業との歴史的な関わりなどは、「知る人ぞ知る」といったところではあるが、瀬戸の一般市民にとっては、今となっては象牙の塔のような存在に映るかもしれない。
しかし、日本で唯一の国立陶磁器試験研究機関として、「陶都」瀬戸を陰に陽に支えてきたのである。その重厚な各種資産が、瀬戸分室の移転統合に伴い、散逸ないし消失してしまう危機が迫っている。
小論は、そのような危機感に立って、「名工研」瀬戸分室とは歴史的・技術的にみると一体どのような存在であり、いかなる意味を持つのかを、瀬戸の一般市民に、さらには行政、陶磁器業界、街づくりに関わる人たちに広く認識してもらい、それにどう対処すべきかの議論を広く巻き起こすことを願い企図して作成したものである。
本稿の最後に述べた提言も、そうした関心と議論を呼び起こす一つの手がかりとして受けとめていただければ幸いである。筆者は別項において、21世紀の瀬戸、歴史的な芸術文化都市の創造に、いくつかの重厚な文化拠点とそのネットワーク化(いわゆるソフトづくり)が不可欠であることを、明らかにしてきた。本稿も、そうした視点と流れを汲むものとして位置づけることができる。
21世紀の初頭を飾る国際博覧会の開催都市である瀬戸は、まさに暮らしやすく働きやすい、また学びやすく、遊び心にあふれた瀬戸の街並みづくり、自然的・社会的・文化的環境の整備が求められている。それがまた、地域のアイデンティティを高めていくことになり、多くの来訪者への“おもてなしの心”につながると思われる。
【 参考文献
】
『名工研陶磁器部門75年の歩み』名古屋工業技術研究所セラミックス応用部、1998年。
『National Industrial Research
Institute of
Nagoya―組織・研究テーマ・規模 ―』名古屋工業技術研究所、1997年。
『セラミックスの歩み―名工試セラミックス部門60年の成果―』名古屋工業技術試験所、 1986年。
『名古屋工業技術試験所最近の15年の歩み(40年史)』名古屋工業技術試験所、1992年。
『名古屋工業技術試験所25年史』名古屋工業技術試験所25年史編集委員会、1978年。
|