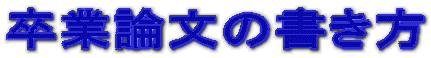
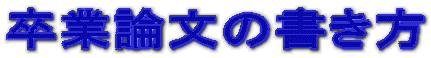
![]() 2001年11月14日作成
2001年11月14日作成
![]() 目 次
目 次
はじめに 2001/11/14
卒論のテーマ 2001/11/14
(1)大きな枠組み
(2)テーマの中で何を書くか
(3)卒論の題目を考える
展開の方法 2001/11/14
卒論のスケジュール 2001/11/14
論文作成の際の文献の扱い方 2001/11/14
卒論関係本の紹介 2001/11/14
![]() はじめに 2001/11/14
はじめに 2001/11/14
4月から始まったゼミももう11月に入った。来年度はゼミの後半2年目にはいるが、最終的にゼミの単位取得に当たっては、卒業論文の提出が義務づけられている。
卒業論文とは自分が大学で学んだことのある意味では総決算である。十分に時間をかけて準備をし、1つの区切りとして思い出に残るものに仕上げてほしい。
締め切りはまだまだ先のようでも、就職活動などで4年生の1年間(実質的には半年と少しである)はすぐに過ぎていく。早めに準備にかかりたい。
![]() 卒論のテーマ 2001/11/14
卒論のテーマ 2001/11/14
(1)大きな枠組み
このゼミでは英語(外国語)教育ということを考えてきた。この路線で卒論を考えると大枠として次のようなテーマが思いつく。
テーマ:私の理想とする英語(外国語)教育
英語(あるいは他の外国語)を勉強する、あるいは覚えるということはどういうことだろうか。また、どのような環境に置かれるともっとも効率的に学習できるのだろうか。自分でもう一度やり直せるとしたら(あるいは遠い将来生まれ変われるとしたら)、どのような勉強をしたいだろうか。自分がやってきた勉強で「あそこで自分は外国語習得に成功するきっかけができた」とか、逆に「あそこで道を踏み外した」とか思い当たるかもしれない。そういうことをきっかけに展開してもおもしろいかもしれない。
(2)テーマの中で何を書くか
さて、テーマはテーマである。こんなものでは卒論にはならない。ここから自分が興味を持っていること、あるいは書けそうなことをじっくり考えて、ここテーマを自分の題材に砕く作業が必要になる。
論文の題材というのはなかなか浮かんでこない。まず、いろいろな文献(本とか論文)を読んでみたり、いろいろな人(友だちでもいい)と話をするといいだろう。このようなことをもとにして、自分は何を書きたいのか、訴えたいのか、ということを考えて欲しい。
例えば次のようなことが題材として考えられるだろう。
現在の学校英語教育の問題点
私が子供に受けさせたい英語教育
小学校での英語教育:その課題
第二外国語の導入の方法
私が考える理想の英語教科書
優れた英語教員とはどういう能力を持っているか
ALT(外国人教員)との英語授業の方法
その他
(3)卒論の題目を考える
そこで話はここからが大事である。これをもっと細かく砕く。これだけで十分に細かいではないか!と思う人はまだ未熟である。また、いったいこれをどうやって細かくしたらいいのか、と不思議に思う人は勉強が足らない。
もとより、その分野で論文を書くということは見た目では本当に重箱の隅をつつくようなことを題目とするのである。そのような重箱の隅をつつくような題目をつけるには、その分野でいろいろな文献を読んで勉強しないといけない。
一見重箱の隅からつつき出してきたような題材ではあっても、その題材を論じるためには幅広い範囲での裏付けが必要である。そのような意味からは、大きな題目をつけても、あるいは十分に練った題目をつけても、勉強するための量には違いがないかもしれない。どんな題材であったとしても、その問題がどんな意義があるかを論じる際には、必ずその分野全体でその問題はどのような位置を占めるのかを考えなくてはならないからである。
題目というのはある意味では問題文である。試験を受けるというのは、ひとさまが作ってくれた問題の解答を作ることになるのだが、論文というのは自分で問題を作る。そこでは、解答が書けそうな問題を設定しなくてはならない。その解答はせいぜい原稿用紙換算で100枚程度の量で書けなくてはならないのである。
解答が書けそうな問題って?と不思議に思うかもしれない。それって八百長では?
そんなことはない。ここで「解答」と言っているのは、解答を引き出すためのさまざまな証拠を並べて、一番可能性が高そうなものはどれかを、読む人がみんな納得できる形で見せることである。そのための段取りを作り、自分で証拠を吟味して、その証拠の並べ方や説明の仕方を考えるのである。
一番細かく砕いた自分の題目を目の前に置いて、さて次はどう料理しましょうか?
![]() 展開の方法 2001/11/14
展開の方法 2001/11/14
卒業論文は最終的には次のような構成になる。
3年生の間に、特に第1章の内容をきちんと固めて欲しい。
第1章:自分が何を論ずるのかを紹介する
(1)自分が選んだテーマの説明
(2)自分がそのテーマを選んだ理由
(3)このレポートで自分が論じたいこととその方法の予告
(4)第2章以降の章立ての説明
第2章:自分のテーマに関して過去に論じられてきたこと
(1)これまで誰がどのようなことを論じてきたか。
(2)自分は(1)についてどう思うか。
(3)自分はどのように論じるつもりか。
(ここでは自分が調べた文献の紹介とそれに対する自分の意見を述べる。どれだけの文献にあたったか、という点と、自分の意見をどのように過去の論点にぶつけるかがポイントになる。)
第3章:自分のテーマを論じる際の方法
(1)どのような方法で論じるか
調査、アンケート、実験等の紹介及びその手順を詳細に述べる。
(2)調査等の結果の報告
(3)調査等に対するコメント(うまくいったこと、今後の課題、問題点などを述べる)
なお、このように調査を行う方法以外に、そのテーマについての代表的な文献を読み、それについての評論を行うことで自分のテーマを深めていくという方法もある。
第4章:第3章で行った調査などに関連させながら自分のテーマを論じる
(1)調査などから何が言えるか(考察)
(2)自分はそれについてどう考えるか。
(3)どのような結論が導き出せるか。
自分の意見を述べる。
意見を述べるときには、具体的にそれぞれに根拠を与えながら、述べるのがこつである。
第5章:まとめ
これまで論じてきたことのまとめ。結論の確認など。
参考文献:
付録(アンケートの全文や全結果などを載せる)
![]() 卒論のスケジュール 2001/11/14
卒論のスケジュール 2001/11/14
(1)これから学年末にかけて、論文の題目(テーマ)を決定する。
その際に、自分がそのテーマを選んだ理由を明確にする。
(2)春学期の間に、自分のテーマについて展開の方法を発表する。
その方法に従って、調査にかかる。
(3)秋学期にに2〜3回中間報告(日程は夏休み終了後に決定)を行う。
(4)提出(^_^;)
![]() 論文作成の際の文献の扱い方 2001/11/14
論文作成の際の文献の扱い方 2001/11/14
1 なぜこんなことを説明するのか
論文を書くときには、自分の意見と自分以外の人の意見を区別して書く必要がある。これは論文の作成にあたって最も重要なことの一つである。
そもそも論文というのは、これまで知らされていたこと以外に新たに自分の独自の考え方を広く紹介するために作成される。そのためには、論文の中で、次の2つを明確に区別する必要がある。
(1)「これまで知らされていたこと」
(2)「自分が新たに主張すること」
(1)は先行研究と呼ばれ、自分がその論文で取り上げるテーマに関して、これまでに行われてきた研究のことである。(2)は自分の主張であるが、勝手に何でも書けばいいというのではなく、(1)の先行研究を踏まえて、そこに何が欠けているかを見抜いた上で、自分の主張を述べなくてはならない。
これが、きちんとできておらずに、単に自分の主張を並べただけの論文は、「これまでの先行研究が紹介されていない」「以前にも同じようなことが言われていたのではないか」「こんなことは今までに聞いたことがあるような気がする」といった批判がされることになる。最悪の場合には、「この論文では先行研究を意図的に隠して、自分の主張のみが新しいように書かれている」「盗作である」と言われることもある。この場合には研究者生命が(相当)危うくなるなる。
論文を書いていく上では、以上のようなことを念頭に置いて作業を進めなくてはならない。従って、逆に、論文を書くためにたくさん(あるいはまだ少しだけ)の本や論文を読んできたと思うが、それらの論文のどこに何が書いてあったかを正確に記録しておく必要がある。なぜかというと、上に述べた(1)の先行研究に関して、いくら詳しく紹介したとしてもその「証拠」を示さなくては、読者からは信用されないからである。「証拠」というのはその主張がどこに書いてあったのかを正確に紹介することに他ならない。
論文の場合に正確な紹介というのは、その文献が「誰が(著者)」「何という本(あるいは論文、記事)で(書名、論文名他)、その本・論文のどのページに」「いつ(発行年)」「どこの出版社から」出されたかを紹介することである。これらの情報は1つずつの引用すべてにつけられなくてはならない。もちろん、こんな詳しい情報を暗記しておけるわけではないから、論文を書こうと思ってテーマに関する文献を読んでいるときに、使えそうな情報はメモを取っておく必要があるし、またそのメモには今述べた情報すべてを書き込んでおかなくてはならない。その情報がないメモは、論文を書くときには、自分の思いつき程度のメモとしてはともかく、論文に直接引用することはできないことになってしまう。文献情報というのはこのように大変重要なものなのである。
2 文献情報収集の方法
文献情報は次のような手順で集めておく。
(1)本・論文などを読むときには必ずメモの用意をしておく。
メモは1ページに1件の情報だけを書く。後でこのメモは順番を並べ替えたりして、構成し直すのでバラバラにできることを前提にしておく必要がある。
このためふつうのノートに書いておくよりも、市販されている文献カード(B6版のカードがよく使われる)の方が、その作業には便利である。
(2)メモには、その本・論文で自分の論文で利用できそうだと思った箇所の引用とそれについての要約、自分の意見などを書いておく。
引用を書く場合には、原著に忠実に書いておく。たとえば、原著で使われいる仮名使いなども正確に引用する。引用を自分の論文に載せる際には原著を同じであることが求められる。ここで不正確な引用を残してしまうと後の作業が倍になる(少なくとも論文執筆のときにまた引用文献にもどって確認をするのは気が遠くなる。また図書館などから借りてきてすでに返した本などはもう一度手続きをしなくてはならない)。
引用と一緒に、その引用の要約や自分の意見を書いておく。引用を書き写してしまうと安心して何か大変なことをしたような気分になるが、実はそれだけでは後で使いにくい。その資料を一目見て何が書いてあるかがわかるようにする。
要約は別に凝ったものでなくてもいい。自分なりの要約で十分である。要約は特に長くなくてもいい。また、点数をつけるわけでもないので正確な要約である必要はない(正確であるにこしたことはないが、自分の偏見が反映されていてもかまわない)。その引用に自分なりの見出しをつけるつもりでやると気楽にできる。さらにその要約についての自分の意見や自分の論文のどこでその引用や情報を使おうと思っているのかをメモしておく。このメモはあくまでもこのときの自分の感想や考えにすぎないので、実際に論文を書いていって、最初の構想通りに使う場合もあるし、また使わない場合もある。さらに、全く別の箇所で活用できることもある(大学の教員のようにプロの研究者になると、このような情報を特定の論文のためだけでなく自分の研究テーマについて常に集めていて、それがある時点まで到達すると、そこで新しい発想が湧いてきたりするのである。もっとも煙のように消えていくことも多いが)。
(3)何度も述べたように、ここで必ず自分が引用した箇所の、文献情報を記録しておく。
文献情報として必要なものは次の通りである。
*著者
*出版年
*書名・論文名
*出版社(論文の場合は掲載されていた雑誌名とその出版社)
*引用した箇所のページ
(4)カードやメモは1つの箱やペーパーフォルダーのようなものに入れておく。
保存しておくものはできるだけたくさんのものが入るものがいい。1つの論文についてのメモは1つにまとめておいた方が便利である。その論文を書き終わって次の論文に移ったら、それらのメモは分類して別途保管する。それまでは1つの場所で管理した方がいい。
(5)カード・メモの材料について
カードやメモは(4)のように保管することを考えると、できるだけ企画が同じである方がいい。メモを取るときにあり合わせの紙の切れ端を使うのも悲壮感が漂って独特の風情があるがそれは能率的ではない。よく使われるのはB6版の京大式文献カードと言われるものである。他にカードにはいろいろな大きさによって種類がある。大きな文房具店に行って見てみるといいだろう(名古屋では東急ハンズなど)。
他にA4サイズやB5サイズの用紙に書き込んでパンチで2穴を開けて閉じておくという方法もある。このときただの用紙でなく、ルーズリーフ用紙を使う方法もある。
もし上で書いた紙の切れ端(たまたま自分の決めた用紙を持ち合わせていなかったときなど)やコピーを切り抜いたものを保管するときには、上で述べた用紙に張り付ける。こうすると規格が統一されて扱いやすくなる。
(6)パソコンを使う方法
カード、メモを作るときに手書きで作ることもあるが(昔はみんなそうしていた)、現在ではパソコンを使うことが多い。これだと、次のような利点がある。
1. 同じことを何度も書く必要がない:
文献情報を作っていると、著者名や書名・論文名、などを同じことを何度も書かなくてはならない。これは実に面倒な作業であるし、間違いも多くなる。これを防ぐために、同じ文献からたくさんメモを作るときには、パソコンのコピー機能を使って同じ部分をあらかじめ作っておけばいい。
2. もう1つの技は、パソコンでそのままカードを作ってしまう方法である。必要に応じてプリントアウトをするが、ファイルの形のままでも利用する。この方法で便利であるのは、引用をする際にそのままファイル間で必要な部分をコピーすればいいことである。もう一つ便利な点は、ある事柄がどこで読んだのか分からなくなったときや、その事柄のカードがどこにおいたのか分からなくなっても、適当なワープロソフトなどの検索機能を使えばどれだけの量があっても一瞬のうちに見つけだしてくれることである。
![]() 卒論関係本の紹介 2001/11/14
卒論関係本の紹介 2001/11/14
(この欄は今後追加していきます。)
3年生に配った本であるが、次の本は特に卒業論文の題目を決める際に読むといろいろと参考になるだろう。
山内志朗(2001)『ぎりぎり合格への論文マニュアル』平凡社新書.
