TOP>NGU EXPO2005研究>第3号(目次)>Ⅳ.瀬戸地域活性化アンケート調査報告 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ⅳ.瀬戸地域活性化アンケート調査報告 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 名古屋学院大学商学部 三井 哲 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 瀬戸商工会議所の地域プランナー派遣事業では、地域活性化に向けて地域活性化研究会を発足し、平成12年度は9月に、地域活性化の具体策を探るためのアンケート事業を実施し、また、これらの成果をもとに、「瀬戸みやげ推奨品」を公募により選定し、認定された商品については、今後、販売拠点の整備や物産展への参加などによって、郷土の土産品として積極的に宣伝し、販売促進していくことになった。 本プロジェクト研究では、このうちアンケート事業に協力し、以下のような報告書を提出した。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【地域活性化研究会に提出した報告書】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| せともの祭りへの来訪者に対するアンケート実施結果 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.調査の目的 瀬戸の地域活性化のための具体策を探るために、毎年、瀬戸市内・外からの多くの来訪者がある「せともの祭り」の会場を利用して、来訪者に対してアンケートを実施し、瀬戸の物産品や観光ポイントの認知度やニーズを把握し、活性化のためのヒントとする。 2.調査の概要 (1) 実施時期 9月10日(日)午後1時より5時まで 今年のせともの祭りは、2日間とも天候が不安定であったが、人出は2日間で54万人に達し、なかなかの盛況であった。こうしたなかで、2日目の午後を使ってアンケート調査を実施した。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(2)実施場所 瀬戸市市民会館2階ロビー、名古屋銀行無料休憩所、愛陶工無料休想所の3箇所にアンケート実施コーナーを設置した。各コーナーには、アンケート実施の立看板を設置して調査をPRし、また、無料休憩所などの施設を利用して机1本、いす2~3脚を用意し、ここで別紙アンケートに記入してもらった。 アンケートの回収状況は(表1)の通りである。 |
(表1)コーナー別回収状況
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (3) 3会場での実施状況 ①瀬戸市市民会館2階ロビー 瀬戸川南に位置する本会館は、催事会場としてはもっとも大きな施設である。1階は、混雑しているため、2階ロビーにアンケートコーナーを設置し、ここを通る人に協力を依頼した。2階では、こども陶芸展・伝統陶芸会新作展・青年研修会新作展などの催事が行われており、回答者は、これらの催事を見るなどの目的を持って、訪れた人が多いとみられる。 年齢的には、子供から大人まで幅広い層の回答が得られたが、4時過ぎに粗品が無くなったため終了した。 ②名古屋銀行無料休憩所 廉売市中心の店が集中している地区で、本休憩所では、ガールスカウトが利用者に呈茶の接待を行った。暑い中のせともの祭りということで、休憩所の利用者は比較的高齢者、また親子連れが多く、アンケートの記入には協力的であったが、4時頃に目標の200件を上回ったため終了した。 ③愛陶工無料休想所 祭催事場のなかでは、西側に位置する愛陶工の建物内で、組合事業と、組合員が行う屋外の廉売市会場を結ぶ休憩所にアンケートコーナーを設置した。この休憩所は、買い物客の待ち合わせ場所に使われていたためか、アンケートに答える人が少なかった。通行客に対してもアンケートへの協力を呼びかけたが、協力者は他のコーナーに比べ少なかった。4時過ぎには、休憩所の利用者も少なくなったことから、4時30分に終了した。 3.アンケートの集計結果 アンケートの設問および、単純集計結果は資料編に示した通りである。以下では、主な項目の集計結果について、簡単にコメントする。 (1)回答者の内訳 602人の回答者の所在地別内訳は、瀬戸市内210、名古屋市142、その他愛知県211人となっており、回答者の3分の2が市外からの来訪者であった。また、男女比は、4:6でやや女性が多く、年齢別では、40~60歳が4割強を占めている。なお、以下では瀬戸市内からの来訪者を(瀬戸)市民と表記することにする。 瀬戸市民以外の来訪者(以下では来訪者と表記)の瀬戸への来訪頻度は、「今回初めて」と「年に1回程度」で5割強となっている。回答者が「年に1回」瀬戸へ来る時は、必ずしも「せともの祭り」の時とは限らないが、回答者の比重が、「せともの」および「せともの祭り」に関心のある人に偏る傾向があることは否定できないとみられる。アンケート実施場所からしても、こうした傾向が出るのはやむをえず、こうしたバイアスがかかっていることを念頭においたうえで、集計結果を解釈することが必要である。 (2)瀬戸の名産品に対する意識 設問2は、瀬戸の名産品に対する市内外の人々の意識を見ようという目的で、瀬戸市民に対しては、何を土産物として持っていきたいと考えるか、来訪者に対しては、何を土産物としてほしいかを尋ねたものである。この結果、市民の6割強が陶磁器を持っていきたいと答え、来訪者の7割強が陶磁器がほしいと答えており、陶磁器が瀬戸を代表する産物としての意識は依然として強く、また、瀬戸市民以上に来訪者の人々の陶磁器に対する期待が高いという結果になった(表2参照)。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(表2)持っていきたい土産物、ほしい土産物
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (注) 1.各欄の上段は回答数、下段は表を縦に見た場合の構成比 2.陶磁器と食品の内訳については、具体的な品名が記入されていたものだけを集計しているため、合計件数と一致しない 3.その他食器には、皿、酒器、コーヒーカップ、食器などの回答が含まれる |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
なお、陶磁器の内訳のうち、件数が少なかったり、表現がやや漠然としているため、分類しにくい回答をまとめた「その他食器」を除いてみると、置物を土産品に考えている人の割合が相対的に高い。 各種食器類のなかでは、持っていきたいものを陶磁器と答えた瀬戸市民111人の8%にあたる9人が食器としているのに対し、陶磁器がほしいと答えた256人の3.5%にあたる9人しか茶碗がほしいと答えておらず、瀬戸市民の持っていこうとするもののと、来訪者がほしいと考えているものとの間に、若干のズレがみられる。 食品では、持っていきたい(ほしい)ものとして、具体的な品目を答えた人の半数が、瀬戸川饅頭をあげている。なお、瀬戸の銘菓に関する認識度を尋ねた問4の集計結果では、瀬戸に銘菓があることを知っているとする人は、瀬戸市民で約5割、来訪者は15%に過ぎず(表3参照)、また、銘菓の具体名をあげた人の8割強が瀬戸川饅頭となっており(表4参照)、瀬戸土産として内外で広く認識されている銘菓はあるとはいえず、そのなかでは、瀬戸川饅頭がやや知られているという状況である。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(表3)瀬戸の銘菓の認識度 (単位:件、( )内は%)
(表4)瀬戸の銘菓の具体名 (単位:件、( )内は%)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 次に、瀬戸の郷土料理として知っている料理、あるいは地元の料理としてよその人に紹介できるものとして記入してもらったものを集計した結果が(表5)と(表6)である。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(表5)郷土料理の認識度 (単位:件、( )内は%)
(表6)瀬戸の郷土料理 (単位:件、( )内は%)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 瀬戸の郷土料理を「知っている」と答えた人は77人で、銘菓を知っているとする人に比べて半減しており、菓子類に比べて、なお認識度は低下する。ただ、五目飯は、忙しい陶器職人が釜を離れずに、食事をとれるようにということで広まった瀬戸特有の食事であり、また、うなぎは、一仕事の終わった職人たちにふるまわれた食事ということで、ともに、陶器づくりと密接な関係をもった歴史のある郷土料理である。 問3は、瀬戸に観光目的で訪れる人を増やして、最近はやりの言葉を使えば、交流人口を増やして、活性化を図る可能性をみようとしたものである。このために、瀬戸にある観光ポイントを観光ポイントとして、市の内外の人がどのくらい認識しているか、また、市民の見方と来訪者との間に、観光資源としての評価に違いがないか、すなわち、観光資源として魅力のないものをさらに整備して、人を呼び込もうとしていないか、などの点についてみようとしたものである。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(表7)観光ポイント
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (注) 上段は回答件数、下段は知っているポイントについては、回答合計を100とした100分比、他の項目は、それぞれのポイントを知っていると答えたものを100とした100分比。なお、複数回か1回限りかの択一式ではないため、両者を合計したものと、知っているポイントの回答数は一致しない。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
集計結果は、(表7)の通りである。せともの祭り会場でのアンケートであることから、当然、知っている観光ポイントとして、せともの祭りをあげた人の割合は9割を超えている。このため、以下では、せともの祭りを除いたものについてみていくことにする。 まず、来訪者がよく知っている観光ポイントは、定光寺、県陶磁資料館、海上の森、岩屋堂、の順となっており、陶磁資料館を除けば、自然景観を楽しむところが多くなっている。これらのポイントは、市民の認識も高いが、これらに加え、市民公園のようなローカルなポイントが上位に顔を出している。また、ボンネットバス、新世紀工芸館、マルチメディア伝承工芸館については、存在を知っている人の割合は、市民で2割前後にとどまり、来訪者に至っては、1割にも達しておらず、これら観光資源のPRがまだ不足していることを示唆している。 何回も行く魅力のある観光ポイントとして上位5番目までにランクされるものは、市民公園を除けば、岩屋堂、定光寺、県陶磁資料館、深川神社、陶祖祭の5ポイントで、評価が一致している。これに対して、1回行けば十分というものは、市民と来訪者の間で、少し評価が分かれるが、共通して上位にあるものには、ボンネットバス、グランドキャニオン、瀬戸公園などである。市民では、この他に、窯神神社や陶製欄干なども上位にあがっている。これらは、総じて、一度体験してしまえば、新たな発見などが期待しにくいものと性格づけることができよう。 一方、来訪者が1回行けば十分としたもので、上位にあるものには、このほか、市歴史民俗資料館と新世紀工芸館がある。市歴史民俗資料館は、複数回行けるとする人の割合も相対的に低いことから、展示内容などが来訪者にとってあまり関心のないものになっていることなどが、原因として考えられる。これに対し、新世紀工芸館は、複数回行けるとする人の割合も総じて高く、評価が分かれている点が注目される。 (3) 2005年日本国際博覧会と観光資源の整備 2005年日本国際博覧会(以下愛知万博)は、入場者数を1500万人として様々な計画の策定を始めている。仮にこの1500万人の入場者の3割が瀬戸市民であっても、1千万人をこえる人が瀬戸市およびその周辺にやってくることになる。この機会を利用して、これらの人々に、瀬戸の魅力をアピールできれば、2005年以降の瀬戸への来訪者数を大きく増加させ、瀬戸の活性化の大きな力となることができる。 設問5は、主として、遠方からの来訪者に対して、万博にやってきた際に、ついでに瀬戸周辺の観光をするために、何泊ぐらい宿泊する可能性があるかを見る目的で実施したものであるが、回答者の大部分が日帰り圏内からの来訪者であるため、大部分の答えが「万博しか行かない」と答えており、所期の目的は達成できなかった。 しかし、(表8)によれば、瀬戸市民で、愛知万博計画を知らないと答えた人の割合が、名古屋市およびその他の愛知県からの来訪者よりも高く、興味を持っているとする人の割合も、名古屋市からの来訪者よりも低いという具合に、地元における関心が依然として低い。こうした状況では、万博を契機に瀬戸の活性化を図るということは、極めて難しいと言わざるをえず、万博開催の意義を市民に周知徹底させることが、喫緊の課題になっているといえよう。 なお、愛知万博には、全体で16%の人が行かないとしていおり、瀬戸から遠ざかるにつれて、その割合が高まっているが、県外の人でも、約7割の人が1回は来ると答えている。また、県外から来る人の45%が、その機会を利用して他の観光地にも出かけたいと考えている。こうした万博への来訪者に、瀬戸の観光ポイントにも出かけようという気持ち、また観光地へ出かけた人には、「再度行こう」という気持を起こさせるような仕組みづくりが必要である。 「最近の観光客は、目が肥えており、単なる名物だけでは呼び込むことができない。彼(彼女)達に来てもらうためには、観光資源に「物語性」などを持たせて、付加価値をつけることが必要である」という指摘がある。そうした観点からは、前述の、瀬戸の歴史と深い関わりをもった五目飯やウナギ料理を活用することが1つ考えられる。これらの料理は、料理名は同じであっても、他の地域とはひと味違った味わいがあると言われているが、それを単に、「瀬戸に来れば、そうした珍しい味わいを体験できる」と売り込むだけでなく、「陶磁器づくりや、窯の火の管理など作業を体験したのち、職人の食べた食事を食べる」までを1つのコースとして売り込むなど、複合的な体験のできる観光コースづくりをして、瀬戸を1日じっくり滞在する魅力のあるまちにしていくことが、「物語性」のある観光資源づくりの一例である。なお、万博への来訪者を対象とした観光資源づくりも大切であるが、拙速のあまり評価を落とすようでは意味がないので、対象によっては、長期的な視点から取り組むということも考えなければならないだろう。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(表8)万博への興味
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 目次へ
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP>NGU EXPO2005研究>第3号(目次)>Ⅴ.瀬戸市産業振興ビジョンに関する提言 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V.瀬戸市産業振興ビジョンに関する提言 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP>NGU EXPO2005研究>第3号(目次)>Ⅴ.瀬戸市産業振興ビジョンに関する提言>21世紀 瀬戸の産業・文化を考える | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21世紀 瀬戸の産業・文化を考える | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 名古屋学院大学経済学部 十名直喜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.はじめに | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ロンドンから北に電車で2時間半ほど行くと、シェフィールドに到着する。シェフィールド(人口約50万人)は英国第4の都市で、かつて鉄鋼の街として栄え、現在も刃物や銀メッキの街として有名である*1。その地での1年間の留学生活(~2000年8月)は、(鉄鋼マンとして過ごし50代で初の海外暮らしの)私にとって、刺激に富むものであった。 国家・地域・個人のアイデンティティあるいは誇りをめぐる日英の温度差を感じたのは、シェフィールドの街中や大学でのディスカッション、あるいは陶磁器のまちストーク・オン・トレントでの企業見学などの際であった。 英国の各地域に点在するまちと自然景観との調和は、現在に息づく「田園都市」(ハワード)のパノラマといえる。また、鉄鋼の街から文化都市への転換を図るシェフィールドには、見事な鉄鋼博物館(「ケーラム島産業博物館」)があり、蒸気発電設備や各種職人の技なども実演されていた*2。英国は近代産業遺産の保存とまちづくりの先進国でもある。世界最初の鉄橋および製鉄博物館などで有名な「アイアンブリッジ渓谷博物館」は、「産業遺産保存のお手本」といわれる。その産業遺産のすばらしさ以上に、産業遺産を生かした文化都市構想が人々を魅了する*3。 帰国後、瀬戸の産業振興ビジョンについて、瀬戸市役所(商工観光課)の方々と幾度か議論し、彼らの熱気に触れる機会に恵まれた。そこで触発された問題意識を手がかりに、瀬戸の産業・文化の今後のあり方について、留学体験も踏まえて捉え直してみたい。 それは、国家・地域・個人のアイデンティティとは何かという点である。とくに、瀬戸のアイデンティティとは何か、将来どうなるのか、という点こそ、21世紀瀬戸の産業・文化を構想するベースになるのではなかろうか。小論は、そうした視点からまとめたものである。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.世界の中の日本、地域 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.1. グローバル化をめぐる議論 瀬戸は、日本の一地域に過ぎないが、国内の各地域だけでなく世界各地と多様な結びつきを持つ。グローバル化は、その結びつきをより身近な、直接的なものにする。 そのグローバル化をめぐって、賛否両論がまさにグロ-バルに渦巻いている。グローバル化を好ましいもの、必然的なものとみなすか、それとも危険なもの、抵抗すべきものとみなすか。アマーティア・センは、グローバル化を「数千年にわたって世界に進歩をもたらしてきた人の移動や貿易、知識の普及を通じた人間同士の相互作用(というプロセス)の延長にすぎない」と捉え、反グローバルもグローバルな思考法に依存しているとみる。問題の本質はグローバル化そのものにあるのではなく、不平等の拡大にあるとみるのである*4。 グローバル化によって、世界はどうなるのであろうか。国際社会の一体化が進むのか、それとも「数多くの文明への分裂・衝突」(ハンチントン)がもたらされるのであろうか*5。 グローバル資本主義像とは一体何か。均質化、アメリカナイゼーションによって単一モデルに収斂していくのか、あるいは(文化に制約されるゆえの多様性・多元性を内包した)複数モデル、すなわち多様な資本主義に分化・発展していくのか*6。 グローバル化をめぐる多様な評価・見解の噴出は、グローバル化の複雑かつ多様な側面を反映したものといえよう。 2.2. 日本型産業・企業システムの改革をめぐる議論 日本の社会経済システムの骨格にあたる産業・企業システムのあり方は、地域の産業・文化のあり方と深くつながっている。 その日本型産業・企業システムのあり方をめぐって、さまざまな議論がみられるが、システムの改編は避けがたいとする点では大方の認めるところとなっている。そうした認識のベースになっているのが、時代文脈および前提の変容論である*7。 戦後、米ソ冷戦体制の下、欧米へのキャッチアップシステムとして比類のない効力を発揮してきた日本型システムは、キャッチアップの達成、冷戦体制の崩壊など、その前提の変化に伴い、従来のような機能が発揮できなくなった。アジアにおける急速な工業化や世界的なIT(情報技術)革命の進行などが、それに拍車をかけている。工業化社会に最適型であった日本型システムは、ポスト工業化社会への移行に伴い最も不適なものになっているともみられる。 システムの変革が避けがたいとすると、どのような方向に改編するかが、次の大きな議論となる。徹底した市場主義か、あるいは日本型システムの良さをふまえた改編か、が問われているのである。徹底した市場主義の導入は、徹底したアメリカナイゼーションでもある。さまざまな規制や既得権益が交錯する複雑多岐なシステムを変革するには、徹底した市場経済の導入が不可欠だとする。 一方、米国モデルという「国際標準」を受け入れざるを得ない面はあるものの金融取引が異常に増大した米英型資本主義のストレートな導入には批判的・懐疑的な見解も少なくない。モノづくりや「勤勉で優秀な国民性」を活かす改編のあり方も提起されている*8。 それは、日本型システムの強み、「日本らしさ」とは何か、そしてそれをいかに伸ばすかというテーマに他ならない。それはまた、日本の国家像、国家目標とは何か、国家としてのアイデンティティの明確化を迫るものである*9。日本の歴史と伝統文化をふまえた国家の個性、独自性、国民の国家意識の明確化が求められている。 2.3. ハンチントン(『文明の衝突』)にみる日本の文明的アイデンティティ論 「日本のアイデンティティとは何か」を考えるにあたって、ハンチントン(『文明の衝突』)にみる文明的アイデンティティ論、とりわけ日本についての分析が注目される。彼によると、21世紀の世界像は、文化、文明が世界の秩序を規定する多極化に向かっている。そして、世界中のあらゆる国々が、自らのアイデンティティをめぐる大きな危機に直面する。「われわれは一体誰か」という問いである*10。 ハンチントンによると、文明と文化は、いずれも人々の生活様式全般をいい、価値観、規範、社会創造、思考様式などを含んだものである。文明=「文化を拡大したもの」とする規定*11などには、疑問や批判も少なくない*12。しかし、日本の文明的アイデンティティを、他のアジア文明とは異質の、それ自体独立した一個の大文明とみる視点は、日本についての極端な自己否定・アイデンティティ否定、あるいは悲観主義の蔓延、への警鐘にもなるものである。 2.4. 日本とは何か(網野善彦) 網野義彦(『「日本」とは何か』)は、多様性、多様な個性という視点から、日本人のアイデンティティに迫る。日本を「孤立した島国」あるいは「単一民族、単一国家」、「均質な社会」として捉える従来の見方を、「虚像」であると批判する。日本を斉一な存在と決め込んで、日本人のアイデンティティを追求しようとすることは、現代日本人の自己認識を大きく誤らせる結果になるというのである*13。 むしろ、それとは大きく異なる日本像を提示する。すなわち、「アジア大陸の北方と南方を結ぶ巨大な掛け橋の一部」*14として、また「きわめて多様な個性をもつ諸地域から構成」されたものとして描くのである*15。 網野によると、現代日本人のほとんどが、自らの国の名前が、いついかなる意味で決まったのかを知らない。これは、「世界の諸国民の中でも、きわめて珍妙な事態」という。正確な自己認識をわがものとするためには、「『日本』とは何か」を徹底的に問い直さなくてはならない*16。 日本の文明的・文化的ルーツは、「日本」国名の由来とも深くかかわる。倭国から日本国への国名変更は、7世紀末、673年から701年の間のことである。689年に施行された飛鳥浄御原令で、天皇、日本国という称号が公式に定められた。対外的に、「日本国」名を最初に使ったのは、702年に中国大陸にわたったヤマトの使者で、周の則天武后に対してである。「日いずる国」=「日の本」としての「日本」は、中国から見たものであり、大陸の大帝国に対し、小なりとも自立した帝国になろうとするヤマトの支配者たちの強い意思が込められていた。この国号の確定された7世紀末は、日本列島の社会の歴史においてもきわめて重要な時期であり、日本人の自己認識の出発点となるべき最重要な事実とみられる*17。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.「瀬戸らしさ」の再評価と創造的発展 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.1.「瀬戸らしさ」とは何か(何であったか) 「せともの」は、日用雑貨の陶磁器製品を総称する言葉として使われてきた。「せともの」の街として知られる瀬戸は、陶土資源や三方を山に囲まれた自然環境、森林資源などに恵まれ、典型的な単一地場産業都市として発展した。1,300年にわたる焼き物の歴史を背景とする文化的蓄積の厚い街である。各種陶磁器関連工業が多様に集積する中小企業の街でもある。食器、ノベルティなど世界に誇る陶磁器産地として栄え、戦中から戦後にかけて瀬戸は「窯焼千軒」ともいわれた。街の中に窯の煙突が林立し、毎日何十本もの煙突が黒い煙を吐き出し、工場の排出物で白濁していた。当時の瀬戸および陶磁器産業を描いた『黒い煙と白い河』(1950年代末)という本の題名そのものであった。 瀬戸らしさとは、まさに上記のようなことであったとみられる。そして、今日では次のような状況も加味してイメージされる。すなわち、転廃業が相次ぎ、工場跡地はマンションなどに衣替えしている。往時をにぎわした商店街もさびれ、古びた街並みが目立つ。ノベルティなど近代産業遺産も散逸の危機に直面しているなどである。 3.2. まちや地域を捉える産業・文化の視点 地域の発展に必要な視点として、アルフレッド・マーシャルは「固有の文化と産業の価値」の発見、および「世界の最も進んだ経験や知識から学ぶ」の2点をあげている*18。 街や地域は、産業や生活の容器であるとともに、その地域に固有の技術やノウハウ、芸術文化を創造する空間でもある。産業を、地域やノウハウと一体のものとして、さらにノウハウや文化の隗として捉えることができる。 多様性と地域の固有性は、現代産業において決定的な重要性をもつ。情報革命に伴い、「情報の意味・内容」(コンテンツ)の重要性がアップしている。コンテンツは、地域の文化的、社会的な伝統や学習の組織によって著しい影響を受ける*19。 歴史、生活、産業にまで視野を広げ、わが「まちなみ」を文化財として見直す動きが広がっている*20。地域に固有の芸術文化価値は、地域において最重要な資源となってくる。地域文化産業財は、最も注目されるコンテンツとなってきているのである。それを活かすには、「異なる目」をもってその地域を見直す人々の受容と活用も大切である*21。 日本では、産業文化への低い理解をどう克服するかという課題もある。とくに、歴史を見る目は古代から中世に向いており、近代日本を直視していない。そのため、「産業遺産は文化である」という認識が定着していないのである*22。国際的な大競争の下、工場や設備の大規模なリストラ・撤去が進むなかで、近代の産業遺産を、自分たちの身近にある産業文化の貴重な資源として見直す必要が高まっている。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.「瀬戸らしさ」の継承と創造的発展 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.1. 瀬戸における技術および産業構造の変化 瀬戸の産業は、最近の30年間に大きく変化した。産業別事業所数では、商業を中心とする第3次産業が全体の62%に達し、製造業・鉱業などの第2次産業が38%と4割を切った。また、就業者数によると1965~95年の間に、第2次産業が60%→42%に減少したのとは対照的に、第3次産業は35%→57%へと大幅な上昇をみせた。第3次産業が第2次産業を上回る傾向は、戦後日本の産業・就業構造にも共通してみられ、産業構造の長期的変化にみる経験則(ぺティ・クラークの法則)を辿ったものである。 第2次産業に従事する市民は、この30年間に28→29千人と、ほとんど増えていない。これに対し、第3次産業では16→39千人へと大幅に伸びた。瀬戸の喫茶店の数は県内でも多い方、といわれるように、飲食店の数が着実に増えた。大型店の進出で個人商店の廃業が目立つが、5年後との集計では5年前を下回ったことはない*23。 工業品出荷額において、かつて7割台を占めた陶磁器は、2割台前半にまで落ち込んでいる。窯業の減少傾向は1991年以降顕著になり、事業所数、従業者数、出荷額は年々下降線をたどっている。陶磁器の販売額は5年間で3割ダウンした。 一方、工業出荷品で多いのは、電気製品、機械部品などである。1998年をみると、電気機器(29.2%)がトップで金属製品(12.5%)と会わせると4割を超え、窯業(23.0%)を大きく上回る。事業所数では窯業が6割と圧倒的で、電気機器(7%)と金属製品を合わせても14%に過ぎず、窯業に小規模企業が多いことを示している*24。工業生産にみるこのような構造変化は、水野に造成された工業団地への大手企業(機械、機器生産)の進出によるところが大きく、陶磁器の落ち込みをカバーしている。 瀬戸市北部に位置する工業団地は、国・県有林の窯業資源採掘跡地を活用して、1969年から90年にかけて3次にわたり愛知県企業庁によって整備されたものである。3団地が一体となって約126haの内陸工業団地を形成している。42工場40社が進出しており(2001年2月現在)、機械・金属関係の工場が多い。この地域産業政策は、瀬戸の土地資源をリサイクル活用した成功例として注目される。すなわち、窯業資源として利用した跡地を工業団地として再生利用を図るゆえに投入コストも節減でき、大都市に近いという地の利なども加わって、機械産業を呼び込み窯業の激減をカバーする役割を果たしたのである。 転廃業が続く陶磁器産業の中で伸びているのが、ファインセラミックスである。1998年10月の愛知県統計では、前年同月比13%増がみられる。この分野において、瀬戸は日本一の中小企業集積地となっている*25。 4.2. 伝統と先端の文化的融合・創造都市 瀬戸をめざして それでは、21世紀における瀬戸のアイデンティティとは何であろうか。窯業を中心に発展してきた瀬戸には、どのような技術的・文化的資産があるのか、未来に継承すべきものは何か、を問い直す必要がある。 瀬戸には、分厚い窯業関連の技術・文化インフラが蓄積されている。例えば、名古屋工業技術研究所瀬戸分室は窯業研究機能を持つ日本で唯一の国立研究機関であり、数十万点の釉薬テストピースなど80年間にわたる研究蓄積には分厚いものがある。愛知県立瀬戸窯業技術センターには陶磁器メーカーの製造を技術的に支援する種々の機能とノウハウの蓄積がある。数多くの経営者や技術者・職人を養成し、輩出してきた瀬戸窯業高校など、多様な研究・教育機関がある。 愛知県陶磁資料館をはじめ瀬戸市民俗資料館、新世紀工芸館、マルチメディア伝承工芸 館には、陶磁器に関連する様々な資料が保存され展示されている。 瀬戸商工会議所の他に、瀬戸には愛知県陶磁器工業協同組合、瀬戸陶磁器工業組合、愛 知県珪砂鉱業協同組合、瀬戸染付焼協同組合、瀬戸石膏型協同組合、瀬戸原型工芸会など 陶磁器にかかわる様々な組合・組織がある。 市内の大学としては、名古屋学院大学、愛知県立芸術大学、南山大学(瀬戸分校)などがあり、瀬戸の産業文化との独自なつながりを持っている。 瀬戸の地方新聞、「日刊とうめい」は、『瀬戸の風』出版などにみられるように瀬戸の産業文化に深い造詣と理解を示し、瀬戸の政治経済から庶民生活に至る様々な情報を紹介発信する情報媒体になっている。瀬戸信用金庫は、助成金などを通じて瀬戸の産業文化や住民活動を支援している。 以上にみるような瀬戸の技術・文化インフラストラクチュアは、窯業関連を中心に幅広く分厚いものがある。それらは、伝統的な窯業関係に特化しすぎているきらいはある。しかし、多面的な交流機能等を付加することによって、むしろ瀬戸固有の産業文化の貴重なネットワークとして活かすことができないものか。新しい感性と視点からどのように創造的に活用するかが問われている。 日本貿易振興会(ジェトロ)の支援を受けて瀬戸市が進めているリモージュ市との産業交流は、そうした新しい試みとして注目される。瀬戸市としては、地域産業活性化に向けた新たな展開を図る起爆剤にしたい、海外との産業交流(デザイン・技術)によって新たな瀬戸のアイデンティティを確立したいという思いがみられる。フランスの代表的陶産地であるリモージュ市は、高級食器の産地であるだけでなく、最近はフランス有数のファインセラミックスの産地となっている。両市の交流はリモージュ側の希望をふまえ、「ファインセラミックス企業との交流」を軸に進められる。推進母体は、ジェトロをはじめファインセラミックスセンター、名工研、瀬戸窯業技術センター、愛知県陶磁器工業協同組合、中部通産局、県、瀬戸商工会議所、瀬戸窯業航行、瀬戸市国際センターおよび瀬戸市などで構成される*26。 世界的にも貴重な資料、約30万点の釉薬テストピースを保管する名古屋技術研究所瀬戸分室は、それらの有効活用を図るべく、膨大な情報のデータベース化を5年前から進めている。2000年8月現在、8千件のデータベース化(「セラミックカラーデータベース化」)し、一部をインターネットに公開している。新規釉薬の開発・改良などにも威力を発揮する*27。地味な作業であるが、伝統的蓄積を情報化時代に生かす貴重な作業として注目される。 瀬戸のブランドを高め、新しい瀬戸のアイデンティティをつくる上で、瀬戸の近代産業遺産に注目し、文化資産として活かす(芸術空間)視点も大切である。例えば、セト・ノベルティを新しい瀬戸のシンボルとして活かす試みも待ったなしといえる。多様な製品群、高度な量産化技術と職人芸の結晶は、瀬戸の貴重な文化的資産である。転廃業が進むなかで、そうした文化的・技術的資産やノウハウが散逸してしまう危機が進行しているからである。セト・ノベルティをアジアとヨーロッパの陶磁器技術が融合した文化的な華として再評価し活かしていく工夫が求められている。 瀬戸の技術・文化インフラストラクチャーは、その蓄積の重厚性・多彩性にもかかわらず、手つかずに放置されているものも多く、十分に活用されているとはいえない。むしろ、新しい瀬戸の産業文化の創造と産業構造変化を促し支える触媒として、活かす必要がある。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.おわりに | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 情報技術革命が進むなかで、ハードよりソフトが、そしてそのコンテンツ(情報の内容)がますます重要になり、感性産業がキーになるとみられる。「特許権や意匠権、著作権など無形固定資産」の蓄積が大切になる。さらに、それらを活かすためには、広域交流ネットワークを構築し、人と人の交流、接触が欠かせない*28。陶磁器産業は元来、モノづくりと文化の融合する産業であり、感性産業としての側面を有している。そこで培われた技術的・文化的資産やノウハウの中に、次世代産業のシーズが眠っているに違いない。 瀬戸は、窯業に育まれた産業都市から産業文化創造都市への脱皮を迫られている。それは、これまでの伝統的に育まれた各種のノウハウや技術的・文化的蓄積を、新しい視点から捉え直し、最新の技術やノウハウと結びつけ、新しい産業・文化を創造するという、新しい物語づくりに他ならない、 温故知新から温故創新へ。21世紀瀬戸の創造的コアは、瀬戸の伝統をふまえつつも拘泥せず、さらにそれを超えるという、守・破・離のプロセスから汲み出される。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [ 参 考 文 献 ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
網野義彦『「日本」とは何か』講談社、2000年 池上 惇『情報社会の文化経済学』丸善、1996年 池上 惇他編『現代のまちづくり』丸善、2000年 加藤康子『産業遺産』日本経済新聞、1999年 佐和隆光『市場主義の終焉』岩波新書、2000年 ジョン・グレイ『グローバリズムという妄想』日本経済新聞、1999年 瀬戸市『瀬戸市の工業(平成10年)』2000年 日刊とうめい、1998.2.17, 1999.2.17, 2000.2.29, 3.29, 4.3, 7.3, 8.10 日本経済新聞、2001.1.3(アマーティア・セン「地球と人間の新世紀」) 〃 、2001.1.7(S・ハンチントン「多極化の裏で孤立の危機」) 〃 、2001.1.10(佐伯啓思「グロ-バリズムの幻想」) 〃 、2000.11.6(鈴木祥弘、原田泉「『日本らしさ』伸ばし強い国」) 〃 、1998.1.7, 2000,11,6, 〃 、1996.7.28(青木昌彦「多様性の意義問う時代」) 〃 、1996.8.11(アブラー・グライフ「歴史分析で多様性理解」) S・ハンチントン『文明の衝突と21世紀の日本』集英社、2000年 森谷正規『技術空洞化論』東洋経済新報社、1995年 読売新聞、2001.1.1 Roger Redfern, Sheffield and its Region, Pitkin Unichrome Ltd., 1999. Sheffield City Museums, Kelham Island, Sheffield City Museums, 1992. *1 Roger Redfern, Sheffield and its region, Pitkin Unichrome Ltd. 1999. *2 Sheffield City Museums, Kelham Island, Sheffield City Museums, 1992. *3 加藤康子『産業遺産』日本経済新聞、1999年 *4 日本経済新聞、2001.1.3(アマーティア・セン「地球と人間の新世紀」) *5 中西輝政「解題」、S・ハンチントン『文明の衝突と21世紀の日本』集英社、2000年 *6 後者の視点から概括したものに、青木昌彦「多様性の意義問う時代」(日本経済新聞、1996.7.28)、アブラー・グライフ「歴史分析で多様性理解」(同、1996.8.11) *7 森谷正規『技術空洞化論』東洋経済新報社、1995年、および佐和隆光『市場主義の終焉』岩波新書、2000年 *8 鈴木祥弘、原田泉「『日本らしさ』伸ばし強い国」(日本経済新聞、2000.11.6) *9 読売新聞、2001.1.1社説 *10 ハンチントン、前掲書、22ページ *11 同上、106ページ *12 山崎正和(『近代の擁護』PHP研究所、1994年) *13は、「ハンチントンの文明概念の粗雑さ」=文明と文化の混同を批判する。山崎によれば、文明は機械的制度的であり、文化は有機的感性的である。山内昌之も、文明=「都市化」、文化=「精神的所産」と捉え、ハンチントンの規定に批判的である(蓮實重彦・山内昌之編『文明の衝突か、共存か』東京大学出版会、1995年)。 *14 網野義彦『「日本」とは何か』講談社、2000年、351ページ *15 同上、35ページ *16 同上、352ページ *17 同上、22-24ページ *18 同上、20-21ページ *19 A.Marshall, Priciple of Economics, Macmillan, 1890, 9th ed.、 馬場啓之助訳『経済学原理Ⅱ』、東洋経済新報社、1966年、第4編第10章 *20 池上 惇他編『現代のまちづくり』丸善、2000年、77ページ *21 同上、11-12ページ *22 同上、32ページ *23 加藤康子、前掲書、 *24 日刊とうめい、1999.2.17 *25 瀬戸市『瀬戸市の工業(平成10年)』1999年3月、11ページ *26 日刊とうめい、1999.2.17 *27 〃 、2000.7.3 *28 〃 、2000.8.10 29 森野美徳「『箱もの』からソフト重視へ」(日本経済新聞、2001.3.24) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP>NGU EXPO2005研究>第3号(目次)>Ⅴ.瀬戸市産業振興ビジョンに関する提言>瀬戸市産業振興ビジョン作成に当たって | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 瀬戸市産業振興ビジョン作成に当たって | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 名古屋学院大学商学部 三井哲 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 瀬戸市産業振興ビジョン作成に当たり、以下の提言をいたします。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.瀬戸市の将来像について | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地方分権が進む中で、地方自治体に求められる役割は今後ますます増大していきます。地方自治体が住民から求められるサービスを着実にこなしていくためには、財政基盤の充実が不可欠であり、そのためには、当該自治体は活力を維持し、発展を続けていかなければなりません。 活力を維持する方策は、大きく分けると、①時代の流れに合った産業を誘致・育成し、その産業の活発な活動によって、まちを活性化していくというものと、②大都市のベットタウン化することによって常住人口を増やし、それに伴って商業施設などが充実することで街を活性化していく、という2つの方向性があるかと思います。 21世紀における日本の構造変化について考えると、少子高齢化は避けて通れない問題であり、今後の少子化による総人口の減少を前提にすると、瀬戸市の場合、名古屋のベッドタウンとしての役割はだんだん低下していくものと考えられます。したがって、②よりも、①すなわち産業活動の活性化を選択すべきであると考えます。 そこで、以下では産業振興による活性化について考えていくことにします。 なお、産業振興としては、研究所や大学を誘致して、本市に通ってくる若者が増えることや、観光資源を目当てに、やってくる観光客が増えることも含めた、交流人口を増加する産業を振興するという観点も含めて考えることにします。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.瀬戸の産業振興とその支援策について | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 効率的に産業振興を図っていく方法としては、旧来からの産業基盤を活用するということが第1にあげられます。しかし、本市の伝統産業である陶磁器産業は、発展途上国からの追い上げなどにより、既に海外市場だけでなく、国内市場においても競争力を失っています。自治体が限られた予算で、この従来の陶磁器産業を支援しても、欧米の有名ブランド並の評価を得るところまでデザイン力を引上げたり、価格競争力を回復するまで生産性をあげることは難しいと思われ、費用対効果からみて望ましくありません。 もちろん、代わるべき産業が育たないうちに陶磁器産業が衰退してしまっては、活力を回復することは極めて難しくなるので、これらの事業者に対するある程度のバックアップ施策も引き続き継続することもやむを得ないと考えます。 また、陶磁器製品のうち、ファインセラミックの分野は、今後も高い伸びが期待されます。したがって、この分野への転換を支援することも重要な施策と考えますが、和洋食器メーカーが現在持っている技術力では、簡単には転換することはできないとみられます。それでも、チャレンジしようという意欲的な企業に対しては、行政が支援することが望まれますが、補助金のような直接的な援助よりも、瀬戸在住の公設の試験研究機関などが、業種転換を希望している業者が参入できるような、新たな素材や用途を開発することに対しての支援したり、あるいは、その成果を情報として提供していくという形での支援などを考えてはどうかと思います。また、万博会場隣接地の新住計画は流れましたが、別途、市内に用地を準備して、ファインセラ分野の民間・公共の試験研究機関を誘致することができれば、いっそう成果が大きくなることが期待できます。 なお、本市では穴田などの企業団地に多様な業種の企業を誘致し、出荷品目の多様化を実現し、陶磁器の単一産業都市から脱皮しました。これによって、ある業種が不振であっても、他の業種がカバーすることで、景気変動の波を小さくすることができます。今後も引き続き、その方針を継続することが望ましく、過大な財政負担を避け、適正規模の用地を開発し、誘致対象としては、研究機関も視野に入れた活動をしていくべきだと思われます。 新しい産業形態としては、メーカー以外に観光産業も考えられます。すでに、陶磁器関連の展示施設などの整備にかかっていますが、昨今のテーマパークの不振にもみられるように、単なる展示だけではじきに飽きられてしまい、初期投資が回収できる前に次の投資が必要になる恐れがあります。これを回避する策としては、観光だけでなく、体験作陶ができるようにするだけでなく、多様な工房を用意し、1回の来訪で作陶できるものから、何回も通ってできあがるものなど、いくつものランクを設けるなど、多くのメニューを用意すると、リピーターの増加が期待できます。また、窯に火入れをし、汗をかいたあと、昔の職人のように、五目飯を食べるという物語性のあるコースを作るという工夫をすると、瀬戸への滞在時間も増え、消費単価の増加も期待できます。 既存の商店街については、一部にやる気のある経営者がいるものの、全体としての盛り上がりに欠けるため、行政が画一的な振興策を押しつけても、うまくいかないと考えられます。そこで、まず、上記のような観光資源の開発をし、瀬戸への来訪者、交流人口を増やし、商店の売り上げが増えるような環境づくりをすることで、やる気のある商店主を増やしていくという方向が当面とるべき道ではないかと考えます。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.まとめ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 以上の考え方をまとめると、本市の産業振興策は、 ① 陶磁器産業に対しては、衰退を支えるために若干の後ろ向きの支援の継続と、フ ァインセラへの転換支援 ② ①に関連し、ファインセラ関連の研究機関を含めた企業誘致 ③ 観光資源を開発、追加して魅力を高め交流人口を増加する。 ④ ③に関連し、交流人口の増加を起爆剤とした商店街の活性化 という方向性を基本に考えてはいかがかと思います。 とくに、企業誘致については、過去の博覧会の事例に多く見られるように、愛知万博を瀬戸のイメージアップの場として積極的に利用することを考え、万博までに用地を整備し、企業関係者に対して、万博への来訪時にこれをPRして成約につなげていくことが望まれます。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 以 上 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP>NGU EXPO2005研究>第3号(目次)>Ⅴ.瀬戸市産業振興ビジョンに関する提言>瀬戸市の産業振興へ向けて | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 瀬戸市の産業振興へ向けて | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 名古屋学院大学経済学部 伊澤俊泰 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.はじめに | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1985年9月のプラザ合意以降の急速な円高により、瀬戸市の地場産業である陶磁器産業は急速に輸出競争力を失い、その産業活力は低迷している。また、これと平行して、尾張瀬戸中心部の商店街では、店舗の老朽化、事業後継者難、および買い物客の減少により中心市街地の空洞化が進んでいる。現在も、日本の製造業の中心的役割を受けもつ愛知県において、そのなかの瀬戸の産業に「元気がない」のは憂慮すべきことである。伝統的産業の衰退はあるものの、瀬戸市は、来る2005年国際博覧会のホスト・シティであり、内外にこの地域をPRする好機もある。 1300年を越えるものづくりの伝統をもつこの産業都市が、再び活気を取り戻すにはどうしたらよいか。万博開催都市としてこのまちのアイデンティティをどこに求めたらよいか。瀬戸市は、このような観点から、数10年ぶりに新たな「産業振興ビジョン」を打ち出すこととなった。 前世紀末から今世紀にかけては、各国で都市間競争の激化が生じている。たとえば、米国に見られるように、これまで政治・経済・文化などさまざまな面で国をリードしていた北部の都市から、近年は、温暖な南部のフロリダ州やテキサス州の中心都市に人口流入が続き、都市間の勢力関係に地殻変動が生じている。日本国内でも、今後の市町村合併を軸とした自治体再編の方向が打ち出されており、これは日本でも同様な変化が起きるきっかけとなるかもしれない。昨年、万博を開催したドイツのハノーバー市は、統一ドイツの地理的中心に位置する利点を生かし、万博開催を期に見事なまでの社会資本整備を達成した。ハノーバー万博自体は、巷間でささやかれているように興行としてみれば大きな失敗であったかもしれないが、それと引き換えにドイツの中心都市としての風格を手に入れつつあるとも言える。あくまで万博開催を一里塚として、その先の都市づくりを目指したものといえよう。 瀬戸市は、ハノーバーと比べれば小さい都市ではあるが、博覧会のホスト・シティとしてどのようなまちづくりを目指すべきであろうか。ここでもやはり、単に万博のための急ごしらえのまちづくりを目指すのではなく、ハノーバーのように長期的視点に立ったまちづくりを考えなければならない。市が打ち出す産業振興ビジョンも、おそらくこのような観点から提示されるものであろう。 本稿では、瀬戸市の産業(工業・商業)が抱える問題の現状を展望するとともに、来る2005年の国際博覧会とその先を睨んだこのまちの活性化に関して私見を述べたいと思う。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.瀬戸の工業 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全国47都道府県には、それぞれその風土・歴史によって培われた独自の性格「県民性」が備わっているといわれる。瀬戸市のある愛知県には、名古屋という日本第4の規模を持つ大都市があり、この名古屋に住む人々の行動様式をとらえて“名古屋学”なるタイトルを銘打った文献も数多くある。このような県民性については、文化人類学的立場からの論考によるものや各地域の歴史的視点から県民性の必然を考察したものなどがある。 こうした文献で語られる愛知県・名古屋(あるいは、尾張地方・三河地方)の県民性(市民性)としては、「無駄遣いをしない堅実性・合理性」が評価される一方で、「流行に対する保守性・消極性」、「商人的性格の一方で外に対し閉鎖的な性格」などもあげられており、いささかネガティヴな印象でもってこの地域が眺められていることも表している。 長引く10年不況の中、全国の企業・事業所の開廃業率は、開業率が低迷する一方で、廃業率が増加し、前者を上回っているのが現状である。愛知県においてこの統計を眺めると、自動車・工作機械・セラミック産業などの強固な製造業基盤に支えられて、廃業率は全国平均よりも低くなっている(1995年~1996年において廃業率3.3%)。その一方で、開業率も全国平均を下回っている(1995年~1996年において開業率3.1%)。すでにできあがった産業基盤は安定し、その堅実さゆえ不況に対する強さを発揮しているものの、新しい分野を切り開く空気がこの地域に欠けているのであろうか。愛知県の「保守性」は証明する1つの事例といえよう。 自動車・工作機械を中心とした産業基盤があるとはいえ、愛知県はいつまでもこのような産業構造に頼ってばかりもいられない。遠く将来を展望するなら、これら愛知県の看板産業はいずれ後発国企業との熾烈な価格競争に巻き込まれることも予想され、今後は、海外移転が加速する可能性もある。日本を取り巻く経済環境の変化に応じて、愛知県の産業構造も変化が求められることとなる。また、すでにぎりぎりまで効率化されたこれら製造業の雇用吸収力も、今後多くは望めない。新産業を愛知に起こす必要性が高まっているといえよう。 瀬戸は、かつて陶磁器産業で賑わった時代において、この産業に従事する職人にとってきわめて住みやすく、多くの職人による地域からの流入があったという。加えて、瀬戸の陶磁器産業は日本全国あるいは世界各国の需要に応じて製品の仕様やデザインを変えて即応する柔軟性を持った産業であった。21世紀の瀬戸の製造業を考える上でかつてもっていた、いや現在ももっているであろうこの柔軟性を大いに発揮する必要がある。 愛知県の製造業について、今後、強化すべき分野としてたびたび指摘されるのは、情報通信に関わるハード・ソフト産業の充実である。このような隙間部分を埋める役割が瀬戸で果たせないであろうか。もちろん、何のシーズもないところにこのような産業を立地させることはできない。陶磁器産業の町「瀬戸」というイメージがあるが、表1に見られるように事業所数、従業員数では窯業土石製品が群を抜いて高いが、業種別出荷額ベースで見ると電気機器が全体の29.2%でトップとなっている。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表1 瀬戸市の工業生産の構成比 (%)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| さらに、伝統的陶磁器産業が一時の勢いを失っている中、近年のIT産業の隆盛(もっとも昨年来これら産業の不況振りがメディアを賑わせているが)に伴い、ファイン・セラミックス産業が勢いを増しており、およそ50社を数える企業が活動している。つまり、瀬戸においては高付加価値の電気機器および電気機器関連の素材産業の下地がすでにできつつあるのである。 瀬戸市は、平成12年度、日本貿易振興会(JETRO)のローカル・トゥ・ローカル(LL)産業交流事業の一環として、高級食器生産で有名なフランスのリモージュ市との産業交流事業を開始した。その交流事業の目的は、①技術開発による新分野の開拓と高付加価値化、②消費者ニーズの多様化に対応するシステムづくり、③デザイン力強化による産地ブランド確立、④産業観光の新たな取り組み、である。 *特に、ファイン・セラミックス産業については、瀬戸がリモージュより先行しているといわれ、これら産業を核とした新規分野の投資および技術交流が期待できる。 瀬戸がファイン・セラミックス産業の集積地域として名を馳せることにより、情報通信産業関連企業を呼び込むことを期待したい。 瀬戸と同じように円高の嵐に見舞われた新潟県の燕市は、伝統産業である洋食器製造業が不振を続ける中、新たな取り組みに挑んでいる。 **燕市は、たとえば洋食器生産においてはプロのデザイナーを起用したデザインと企画重視の形態に移行しつつあり、ブランド化をすすめることで、内需の掘り起こしを行っている。また、これまで蓄積された金属材料加工技術を生かし、ゴルフ・クラブやカメラ・ボディの生産に転換する動きも加速している。これまで培われた企業間のネットワークを生かし、地域の重層的な生産構造の強みを生かした試みである。 瀬戸がリモージュ市と提携することは、伝統的陶磁器産業においてもかの市がもつデザイン力やブランド・イメージ確立の手法は、瀬戸にとっても大いに参考になるであろうし、ファイン・セラミックス分野での瀬戸の優秀さを広くアピールするチャンスともなり、新たな投資チャンスを期待できる。 国内随一の技術を持ち、しかも豊富で良質な土に恵まれながら、これまで確固としたブランド・イメージを持たなかった瀬戸がこのような交流事業を期にイメージ転換を図ることが望まれる。そして、瀬戸がもつ重層的な技術の蓄積を生かした新たな産業展開が必要である。何もシーズがないところにまったく新しい産業を起こすのではなく、すでに存在する資産の有効活用がなされるような産業振興を望みたい。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
*日本貿易振興会(JETRO)「平成12年度ローカル・トゥ・ローカル産業交流事業について」(http://www.jetro.go.jp/ove/nag/p0004052.html )より **日本経済新聞、平成12年6月4日朝刊、列島プラザ「食器産地、円高からの反攻」を参照。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.瀬戸の商業・まちづくり | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中心市街地の空洞化は、全国的なものである。かつて駅前などの好立地を生かし、商業の中心であった各都市の中心市街地は、各家庭への自動車普及にあわせて、大規模駐車場を備えた大手スーパーの郊外立地が進んだことや、中心市街地の人口減少、商店街店舗の新陳代謝の遅れなどにより、めっきりその機能が衰退している。 瀬戸も例外にもれず中心市街地の衰退が進んでいる。しかし、瀬戸においてはこの衰退化を食い止めるチャンスがあるのではないかと私は考える。たとえば、愛知県において瀬戸のサイズに近い他の10~20万都市と比べると、瀬戸はまだ多くの住民が中心市街地に住んでいるのである。瀬戸の中心市街地の人口密度は53人/haであり、隣の春日井市のそれ(35人/ha)に比べ大きい(数字はいずれも国勢調査に基づく)。この瀬戸の数字は、県内の他の10万以上都市と比べてもそう変わらない。確かに、瀬戸は他の都市と比べてやや高齢化率が高いが、近年、中心市街地周辺に集合住宅の建設が続いたこともあり(もちろん景観上美しいものではないが)、人口が急減しているわけではない。瀬戸の中心市街地の衰退を食い止めるにはこのような中心部人口の維持および世代交代を円滑に進めることが必要である。 若い世代が中心部に魅力を感じ、住みついていくためには、今後の中心市街地のまちづくり、設計に気を配らなければならない。現在の名鉄尾張瀬戸駅前は周知のとおり、主要な自動車交通路となっており、その往来が激しく、残念ながらまちを散策する環境にない。近年は、この駅前道路一帯で、従来の道路沿い店舗をセットバックする形で歩道の幅を広げ歩行者に気を配っているが、これは反面、自動車の道路走行にも利便を与え、交通量がむしろ増加する可能性もある。むしろ、駅前への自動車流入を減らす方向への交通政策が必要である。中心市街地の周辺に駐車場を多く設けたり、中心部を避ける迂回路を設けるなど公共交通以外の流入を避ける方向への改善を望みたい。 2005年の愛知万博の際には、国内外の多数の人々がこのまちを訪れるであろう。瀬戸市が提唱するフィールド・ミュージアム構想が実現すれば市街地のあちらこちらにゲリラ的な小規模店舗・建築物が出現すると思われる。ぜひここを訪れる人には、それらを歩いて気の向くまま回れるようなゆとりある町並みであってほしい。訪れる人にやさしい町だからこそ住む人にとっても魅力的な「まち」となるのである。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP>NGU EXPO2005研究>第3号(目次)>Ⅴ.瀬戸市産業振興ビジョンに関する提言>瀬戸市における人流れと小売業構造 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 瀬戸市における人流と小売業構造 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 名古屋学院大学経済学部 大石邦弘 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.はじめに | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1980年代後半から加速したグローバル化、規制緩和の波は、90年代のバブル経済崩壊後の低成長とあいまって、日本経済の様々な側面に構造改革を強く求めることになった。商業分野においても、先に述べた潮流の中で、大幅な構造改革が引き起こされ、現在も継続している。日本の商業は、この10年間で、店舗数、年間販売額、従業者数の3つの指標で、全て減少を続けている。特に、この傾向は卸売業において顕著である。これは、海外の大規模小売業態の日本進出などを契機に、複雑だといわれてきた流通構造の簡素化がはかられてきた結果といえなくもない。その意味では、必ずしも悲観的なことばかりではないのであろう。しかしながら、99年の商業統計調査では、小売業の年間販売額が前回調査と比較し、調査開始以来のマイナス(97年比で-8.0%)を記録したことが注目される。バブル経済とその崩壊を経験し、また近年の先行き不透明な景気状況に直面する消費者が、価格や品質に関して敏感になっているとともに、所得不安を抱えて消費抑制を行っているためと考えられるが、このままでは日本の商業は、縮小均衡に陥る危険性もはらんでいるのである。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日本の商業 店舗数(店)・販売額(百万円)・従業員(人)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資料).通産省『商業統計表』 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| マクロ経済のこのような状況に加え、特に小売業で注目されるのが、既存の小売業態の衰退、またそれとともに問題化してきた商店街の衰退である。郊外型の大規模小売店舗に顧客を吸収されるだけではなく、消費者のニーズとの間で、品揃えや価格の面でミスマッチを生じているためとも考えられる。一面では、時代の流れという側面もあろうが、例えば商店街の衰退は、地域住民への消費財供給という本来の小売業の役目を後退させることにもなり、住環境や中心市街地の活性化という側面から看過しえない問題ともなる。さらに、高齢化が進展する中で、「歩いて暮らせる街づくり」(2000年10月の「日本新生のための新発展政策」)という都市のあり方が重要になってくるであろう将来展望からも、この問題は重要となってくる。 さて瀬戸市の商業も、基本的にはマクロ状況と同じような推移を続けている。ただし、個別の指標では明るい動きもみられる。店舗数では、90年代後半にかけて減少幅は縮小し、卸売業の店舗数は99年には増加に転じている。また、販売額も小売業は、マイナスを続けているものの、卸売業は増加に転じており、商業全体でも増加傾向にある。 一方、従業員数をみると、99年には前回比11.0%となり、日本経済全体では、縮小を続ける雇用機会が、瀬戸市に限ってみれば雇用吸収力を復活させたとみられる。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日本の商業 店舗数(店)・販売額(百万円)・従業員(人)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資料).瀬戸市『瀬戸市の商業』、愛知県『あいちの商業』 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.分析の視角 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 先にみたように瀬戸市の商業は、日本全体からみれば比較的良好にみえるかもしれない。しかしながら小売業に絞ってみれば、従業員数のみ増加に転じているものの、店舗数や販売額は減少を続けている。地域住民の暮しやすさにとって重要な要素である小売業の推移には、問題点が多いといわざるをえない。 また、瀬戸市中心市街地の活性化という問題も、他の地域と異なることなく厳然として存在する。尾張瀬戸周辺の銀座通商店街と末広通商店街の空き店舗数の推移は、93年にはあわせて13店舗であったものが、2000年には24店舗にまで膨らんでいる(瀬戸市商工観光課調べ)。瀬戸市のターミナル駅近辺として絶好の立地条件にあるはずの商店街に、空き店舗が増加している原因はどこにあるのか。既存の小売業態の衰退、一方で郊外型店舗の進出と、日本各地に存在する問題がここでも表出しているのである。 本論では、地域住民に密接に関連する小売業に焦点を当て、瀬戸市内にどのように小売店舗が分散や集積しており、その各店舗が顧客をどれくらい吸引しているのか、あるいはいないのかを確認する。 また、モータリゼーションが進展した日本は、これまでのように居住空間に密接した小売店舗の立地を必ずしも求めているものではないかもしれない。そこで、小売店舗の立地と人の流れを中心にした分析を行い、消費者のライフスタイルと今後の小売業のあり方についても考えていくこととする。 なお、小売業構造を分析するにあたり、吸引度指数という指標を用いる。一方で、小売業の効率性をはかるものとして、売場効率(売場面積当り販売額)を用い、小売業の構造とその効率性を複合的に分析してゆく。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.瀬戸市の小売業構造の実態 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 瀬戸市内には、連区という地域グループが存在する。ここでは、その連区ごとに小売業をまとめることにより、連区相互の小売業構造と効率性を分析する。 小売業の構造をはかる指標として、吸引度指数という指標を用いるが、これは、 吸引度指数=当該連区人口当り小売販売額/瀬戸市人口当り小売販売額 と定義される。 この指数が1以上ということは、当該連区は、瀬戸市の平均小売販売額以上の販売を達成していることになるので、その連区は他の連区から顧客を吸引していることを示す(より正確には、他の連区に流出する顧客よりも当該連区に流入する顧客が多い流入超過を示す)。つまり、他の連区よりも比較的魅力的な小売業者が存在していることを示すともいえる。他方1未満ならば、その連区は顧客が他の連区に流出していることを示す(より正確には、流入する顧客よりも、流出する顧客が多い流出超過にある)。 連区ごとの小売関連の最新データは、97年のものでありここでは、そのデータを基本に、85年から3年ごとに実施された商業統計調査と比較検討していく。 分析を行う前にまず留意しておかねばならないことは、吸引度指数が、各地域の小売業者の魅力を示す指数であるといっても、ここでは人口10万強の瀬戸市内という小さな範囲での指数に過ぎない。すなわち、連区ごとの小売業構成の相違が吸引度指数に大きな影響を及ぼす可能性がある。 また、市内における分析では吸引度指数が高くても、それは市内の平均的水準からみて高いということであり、必ずしも他市町村から顧客を吸引できるくらいに魅力ある小売業者が存在するとは限らない。この後の分析で、市内各連区ごとの吸引度指数を算出しているが、愛知県内における瀬戸市全体としての顧客吸引力は、周辺市町村に比べ小さいことは留意しておかねばならない。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
瀬戸市周辺の吸引度指数
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| なお、瀬戸市内の連区は16連区あるが、ここでは水北連区(現、水野連区)に西陵連区を含め、また原山台、萩原台、八幡台は菱野団地としてまとめることとする。その結果、対象とする連区数は13となる。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
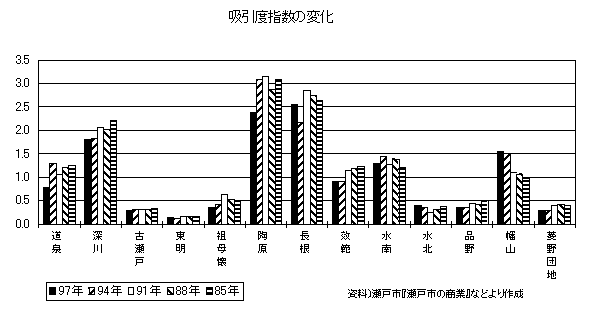 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(不鮮明な場合は画像をクリックしてください。) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 97年において吸引度指数が1を超えているのは、13連区中の5連区である。瀬戸市中心部にあると思われる古瀬戸や祖母懐連区の吸引度が低いこと、道泉連区の指数が97年に1を割り込んだことが注目される。また幡山連区が近年、吸引度を高めていることも注目される。 これまでみてきた吸引度指数は、小売業全体で算出したものである。消費者が手軽にかつ頻繁に購入するような財である最寄品に焦点を当て、その代表と考えられる飲食料品に限り、データの揃う97年と94年の2時点で、吸引度指数を算出してみよう。このような財こそ、生活の場に密着した購買行動が行えるか否かを捉えるには、より適切な財であると考えられるからである。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
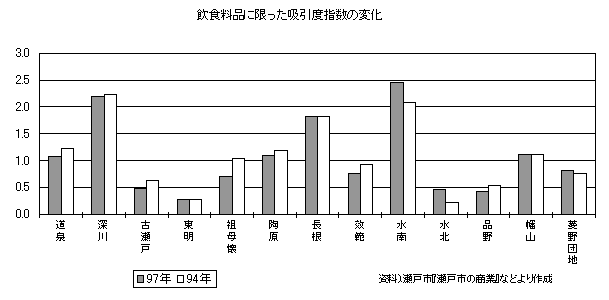 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(不鮮明な場合は画像をクリックしてください。) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| この時は1を超える連区は、6連区となる。小売業全体では、1を下回る道泉連区が、飲食料品に限れば、今もって1を上回っているからである。小売業全体の指数と比較して、陶原連区の吸引度が大きく低下していること、それに対して、水南連区の吸引度が大幅に上昇している。陶原連区では、飲食料品以外での吸引力が強いこと、水南連区では飲食料品以外の吸引力が逆に弱いことを示している。 個別連区の事情を考慮した分析を行う前に、算出された吸引度指数と小売業者の効率性とを関連させ、分析を行う地域を分類し、その特徴を探ることにする。 小売業の効率性を測る指標には、店舗当りの販売額(店舗効率)や、従業員当りの販売額(人的効率)など様々な指標が考えられるが、建野他(1999)による九州各県における分析を参考にして、ここでは売場面積当り販売額(売場効率)をもって、小売業者の効率性を計測することにする。そして、これらの結果をもとに、以下のような地域タイプに分類する。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地域タイプの分類表
上記の分類表に従い、85年調査時と97年調査時とで、地域タイプの変動をみると、 <1985年調査>
<1997年調査>
資料).瀬戸市『瀬戸市の商業』、『瀬戸市統計書』により算出 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 売場効率性において、中心市街地といわれる地域の効率性が比較的低く、郊外に位置する地域の効率性が高い傾向にある。これは、85年と97年のいずれの調査によっても見出される。その意味で、効率性の点で地域間の2極化が常に存在することがわかる。従来型店舗の多い中心市街地は、店舗の拡大などの改革を時代の潮流にあわせてなかなか行い得ないことを示している。 また85年と97年の調査を比較すると、効率的吸引地域が2から3地域へ増加しているのに対して、非効率的流出地域も3から5地域に増加している。小売業において瀬戸市内では、いわゆる「勝ち組」と「負け組」の2極化がこの10年間で拡大してきたことがわかる。 では、吸引地域の5連区の状況を、もう少し詳しくみてみよう。 まず長根連区は、一貫してⅠ-Aタイプに属しているが、国道363号線(瀬港線)や県道名古屋瀬戸線(瀬戸街道)沿いに立地するロードサイド型店舗による吸引力と考えられる。先にみたように、この地域は飲食料品に限っても吸引力が強く、多様な小売業者の展開によって吸引力を保持していることがわかる。また市内平均と比べれば比較的大規模店舗(97年1店舗当り売場面積120.1㎡)であり、また駐車場などを広く確保することで、顧客をひきつけているのであろう。 陶原連区は、名鉄尾張瀬戸駅から南西に伸びる地域を指し、中心市街地に属する連区である。ここには、大型スーパー(売場面積5,005㎡)の立地によって、強い吸引力を保持できていると考えられる。ただし、飲食料品に限ってみると吸引度指数は、1近辺まで低下することから、この地域の吸引力は最寄品というよりも買回品に関して強い吸引力があると考えられる。同地域は、市内小売店舗の10%強を保有しており、商業集積の度合いが強く、住民100人当りの店舗数(店舗密度)をみると、深川、道泉両連区に次いで高い(97年で2.1)。しかしながら、販売効率は瀬戸市平均をやや上回るに過ぎず、効率性からみれば今後、非効率店舗の廃業が増加し、激変が続く地域であると予想される。 幡山連区は、市の南西部を占める地域である。長根連区から続く国道363号線と、豊田市へ到る国道155号線を有している。吸引度指数が調査期間中、一貫して上昇した唯一の連区である。特に、国道155線近くにショッピングセンターが形成され、90年代吸引力を高めたものと考えられる。ただし、店舗数の増加に対応してこの地域の売場面積は、85年から97年の間に、4倍(13連区中トップ)にも拡大しており、売場面積の拡大スピードに比して吸引力は高まっているとはいえない。つまり、販売効率の面ではA分類に属しているとはいえ、売場効率は一貫して減少している。大型ショッピングセンターのメリットを十分に活用していないといえよう。実際、2001年2月にはこの地区の大型店舗が閉店しており、そのような原因に根ざしているものと考えられる。 深川連区は、尾張瀬戸駅の東部に位置し、末広町商店街を地区内に有する。飲食料品に限った吸引度指数では、水南連区に次いで高い吸引力を保持していることから、最寄品を中心とした吸引力を、商店街が保有していると考えられる。しかしながら、売場面積の減少に対して、売場効率は改善していなことから、全体としての効率性は良いとはいえない。店舗数も減少の一途(85年と比較すると25.8%の減少)をたどっており、現在は吸引地域に分類されているが、近い将来に流出地域に転換する可能性が高い。 水南連区は、名鉄瀬戸線新瀬戸駅から北東方向へ広がる地域であり、国道155線や愛知環状鉄道が走る地域でもある。小売業全体の吸引度指数は、1以上の地域の中で最低であるにも関わらず、飲食料品に限ると、全地域の中で最高の吸引力を示す。新瀬戸駅周辺の食料品スーパーを中心に最寄品の吸引力を強く持った地域であるといえよう。しかしながら、この地域の売場効率も極端に悪く、効率性だけで判断すれば、市内で下位の地域といえる。そのため、今後この地域では効率的な店舗とそうでない店舗の選別が激しくなり、店舗の開廃が進展するであろう。2000年秋には、大型店舗が新瀬戸駅前に出店しており、その意味での競争は、今後いっそう激化するものと考えられる。 以上の5つの地域が吸引地域であるが、次に流出地域の中で注目される地域をいくつか取り上げ、その状況を分析してみる。 效範連区は、名鉄瀬戸線水野駅を中心に尾張旭市まで広がる地域である。水野駅近辺の效範西部商店街と、新瀬戸駅南側の新瀬戸商店街を含む地域である。ここは、90年代半ばに吸引地域から流出地域に変わった。また、尾張瀬戸駅駅周辺の中心市街地からは離れているが、瀬戸市内の全小売店舗数の10%強を占めており、深川、道泉の両連区よりも店舗数が多いことになる。店舗数の減少傾向にも関わらず、販売額は目立って伸びず、その結果は販売効率も平均では上回っているものの、低下傾向を続けている。つまり、非効率店舗の廃業が続いている状況であり、吸引力の回復には到っていない状況がみられる。 道泉連区は、尾張瀬戸駅から北方に広がる領域である。中央通商店街、銀座通商店街が存在し地域内に100店を超す小売店舗を有するものの、吸引から流出地域に変わることになった。ただし、飲食料品に限ってみれば、吸引度指数がかろうじて1を上回っており、最寄品の供給という面では、依然として地域住民に貢献できてはいるが、それ以外では吸引力を喪失したものと考えられる。また、販売効率では、平均を大きく下回っており、さらに1店舗当りの従業員数は3人前後で変化がなく、店舗の大規模化などの構造変化が進まず、低迷を続けている状況がうかがわれる。 品野連区は、市内東部に広がる領域である。春日井市から岐阜県多治見市や土岐市などと境を接する地域である。一貫して流出地域であり、この傾向は飲食料品に限ってみても変わりがない。売場効率は、効率的な分類から非効率な分類へと移動しており、全般的に低迷している状況がうかがわれる。店舗数は減少を続けており、店舗当り売場面積は若干上昇しているが、店舗当りの従業員数は3人前後で推移しており、旧来型の店舗が今なお小売を続けているという状況が推察される。この地域は、多治見市へ比較的容易にいけることから、他県に購買機会が流出しているものと考えられる。その結果、新しい小売業態の展開も手控えられているのであろう。 瀬戸市全体の吸引力は低いものの、その地域の中では、郊外に位置する地域の吸引力が比較的強く、中心市街地といわれる地域の低迷は大きい。多くの都市と同様に中心市街地活性化の問題が重要になってくる。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.瀬戸市の人流 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 瀬戸市内における小売業の状況をこれまでみてきたが、買手となる人の流れは、この時期変化してきたのであろうか。瀬戸市内に関わる人流に着目することで、先にみてきた小売業の地域別の盛衰との関連を検討する。 まず、5年ごとに行われる総務庁『国勢調査報告』を用いて、瀬戸市に関わる人流の概要をみておこう。常住人口(夜間人口)と昼間人口との推移をみると、常住人口が増加しているのに対し、昼間人口はあまり伸びていない。そのため、就業や通学で他市町村へ人が流出している実態がわかる。これは、年を経るに従い、増加傾向をたどっており、95年の調査では、昼間の人口は夜間の90%弱にまで減少している。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
瀬戸市の常住人口と昼間人口の推移 (人)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 実際、通勤や通学にどれくらいの人数が、瀬戸市へ流入し、瀬戸市から流出しているのか、詳細の発表されている最新時点の95年と、10年前の85年を比較してみよう。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<1985年調査>
<1995年調査>
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全体では流出超過には違いないが、通勤と通学別にみると、通学者の場合は、若干ながら流入超過になっている。また、通勤と通学いずれの場合も、流出入する人数は増加している。つまり、何らかの形で瀬戸市に関わる人口自体は、85年では138,650人であったものが、95年には149,038人にまで増加しているのである。 瀬戸市に関わる人口は増加しているわけであるが、その人口がどのような人の流れとなっているのか。そこで、瀬戸市の中心的な鉄道駅である名鉄瀬戸線の尾張瀬戸駅について、年間乗車人員を定期使用とそれ以外に分けてみると以下のようになる。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
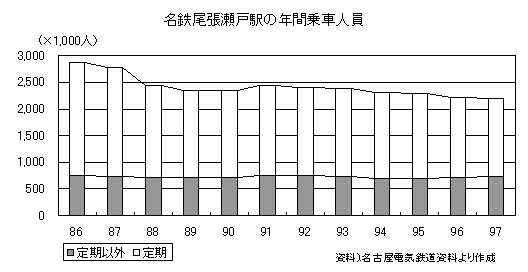 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(不鮮明な場合は画像をクリックしてください。) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 瀬戸市の中心駅であるはずの尾張瀬戸駅年間乗車人員は、近年減少を続けている。しかも、減少の大きな原因は定期券を使う乗客である。それ以外の乗客は、あまり変動していない。定期券利用が大半であるはずの通勤や通学で瀬戸市を出入りする人流は拡大しているのに、公共交通機関の役割は逆に低下していることになる。このことは、通学者はともかく、通勤者の多くが乗用車を利用していることを予想させる。 そもそも愛知県の乗用車保有率は、全国平均より高い。99年で、人口に対する乗用車の保有率は、全国平均が0.39なのに対して、愛知県は0.46である。また、1世帯に保有率でみても、全国が1.05なのに対して、愛知県は1.32となる。ただし、瀬戸市に限ってみると、人口に対する保有率は0.40、世帯に対する保有率は1.13であり、県内で保有率が特に高いわけではない。それにも関わらず、公共交通機関の利用がのびてこないことは、通勤者のほとんどは、乗用車を利用しているということになろう。 通勤や通学をする人の流れだけでなく、先の表にあった市内で生活を営む人たちの流れはどのようなものか。愛知県の『消費者購買動向調査―尾張部における動向 平成13年』は、中学2年生のいる世帯に対してアンケート調査を行った結果である(有効回答数506)。当該世帯の中で主に買い物を行う人物が、最もよく利用する地域を回答してもらった結果が、次の表にまとめられている。これによれば、瀬戸市の購買地域は、明らかに市内から市外、特に尾張旭市へ流出している。公共交通機関の利用は先の図からも読み取れないことから、ここでも乗用車の利用がこれら購買行動を支えていることが予想される。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
瀬戸市住民の購買地域 (%)
調査対象の関係上、回答者の年齢層は、30~40歳代が95.3%を占める。 資料).愛知県『消費者購買動向調査結果報告書』より作成。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 実際、交通量調査をみると、瀬戸市内を走る幹線道路の交通量は、乗用車を中心に飛躍的に増加している。特に、長根連区から尾張旭市方面につながる道路(国道363号、県道61号)の交通量が、台数と伸び率ともに大きいことが注目される。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
乗用車(軽を含む)の交通量変化 (台)
*:1985年調査地点は城屋敷町。**:1985年調査地点は共栄通6丁目。 資料).愛知県『全国道路交通情勢調査』より作成 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 瀬戸市に関わる人口は増加しているのも関わらず、増加した人の流れは、車による流れとなり、いわゆる中心市街地への来街は増加せず、瀬戸市郊外の商業地域に向かっていることが確認できる。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.小売業構造の今後の展望 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 瀬戸市における小売業の問題点は、顧客吸引力が弱く、周辺都市に顧客が流出していること、また市内に限れば、中心市街地の低迷が今後も増大する可能性が高いことである。 このような状況に陥った原因は、既存小売業の消費者ニーズとの乖離が一番であろうが、消費者のライフスタイルに乗用車が重要な位置を占めるようになったことも大きな原因として考えられる。車による移動距離の拡大は、最寄品ですら市内で購買する必要を減じさせることになった。また、駐車スペースの問題から、購買先は広い駐車場を持つ郊外型店舗に向かうことになった。 消費者のライフスタイルに車を欠かせないものとして認めていく限り、車の特性にあった店舗展開がどうしても必要となろう。すなわち、駐車スペースの広く確保できる郊外型店舗の立地を求めることになる。それは、アメリカ式ライフスタイルと非常に似通ったものとなっていくであろう。行政としても、現在のライフスタイルを前提とするなら、瀬戸市郊外への店舗誘致、もしくは近隣都市への道路整備を行うことが必要となる。この場合、中心市街地の問題は微妙なものとならざるをえない。すなわち活性化のためには、中心市街地内に大きな駐車スペースを確保し、乗用車で来街できる条件を整えなければならない。瀬戸市の場合、多くの主要幹線道路は、市の中心部を通るルートになっており、顧客を呼び込める可能性はあるが、逆に現状よりもさらに悪化する交通渋滞の解決に迫られることになろう。片側1車線の道路状況では、多くの顧客を呼び込むには不都合である。 他方、車を前提としたライフスタイルから離れる場合も考えられなくはない。少子高齢化がすでに現実のものとなりつつある現代、また地球環境の保全、二酸化炭素の排出抑制が叫ばれる中、20世紀型の車を中心とした構造も変化を要請される可能性がある。高齢者世帯が増加する中で、これまでのように乗用車を使って郊外型店舗へ買い物に行くというライフスタイルは維持できるのか。1で指摘したように、「日本新生のための新発展政策」で提言されている「歩いて暮せる街づくり」という視点が必要になってくるのではないか。この場合には、小売業の活性化という視点だけではなく、住まいとしての街、行政サービスとしての街づくりなど、複合的視点からの計画が必要となる(小林他(1999)、関根他(1998)にも同様の指摘がある)。例えば、乗用車を使わないために、公共交通機関の充実(バス、鉄道)が必要となる。また、中心市街地には、小売店舗だけではなく、飲食店、娯楽施設、公共サービス関連の施設が立ち並び、来街した住民の色々な欲求がワンストップで達成されるようにならなければならない。 最後に、瀬戸市における小売業構造の将来展望と行政の政策支援を考えるにあたり、短期的視点と中長期的視点に分けてまとめておこう。 短期的には、郊外型店舗の誘致と道路整備によって、市内の吸引力の確保、もしくは市外アクセスの確保をはかる。中心市街地には、昼間は、高齢者もしくは学生・生徒にターゲットを絞った商品展開を、一方、夕方から夜間にかけては就業者の帰路に寄れるような商品展開と営業時間の延長、最寄品や買回品なら例えば女性用に絞った店作りが必要になろう。時間帯にあわせて瀬戸市に滞在する購買層へターゲットを絞った店作り、商品展開が必要である。 他方、中長期的には、歩いて暮らせる街づくりを目指すため、郊外型よりも一層地域密着的な小売業の立地政策が必要になる。その時、再び中心市街地の特性は認められることになろう。ただし、小売業振興だけでは充分ではなく、娯楽施設、飲食が出来る施設、さらには行政サービスの享受も可能となるような都市の再設計が必要となる。例えば、市役所の機能の中で、住民サービスに不可欠な部分を中心市街地に出張所のような形で呼び戻す。飲食店や娯楽施設、また教育施設の立地を促進する。そしてなによりも、多様な年齢層の住民をその周辺に住まわせる住宅政策が必要になってくるであろう。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| <参考> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小売業における連区別諸指標
資料).瀬戸市『瀬戸市の商業』などより算出。
資料).瀬戸市『瀬戸市の商業』などより算出。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【参考文献】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小林重敬・山本正堯(編著)(1999)『新時代の都市計画 3.既成市街地の再構築と都市計画』、ぎょうせい。 関根孝・横森豊雄(編著)(1998)『街づくりマーケティングの国際比較』、同文舘。 建野堅誠・岩永忠康(編著)(1999)『都市小売業の構造と動態』、創成社。 通商産業省大臣官房調査統計部(編)(2000)『2000 我が国の商業』、通産統計協会。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 次へ 目次へ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||