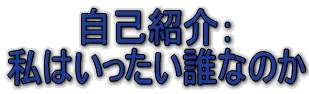
![]()
| 目 次 | ||
| 2005年 | ||
| 第21日目 2005年謹賀新年 | 2005/ 1/ 2 | |
| 2003年 | ||
| 第20日目 再び新しいパソコンと私 | 2003/12/8 | |
| 第19日目 ソウル雑感 | 2003/9/23 | |
| 第18日目 2003年度の私 | 2003/4/3 | |
| 2002年 | ||
| 第17日目 「卒論とは何か」 | 2002/1/15 | |
| 第16日目 新年(2002年)の私 | 2002/1/5 | |
| 2001年 | ||
| 第15日目 音楽と私(この頃) | 2001/10/20 | |
| 第14日目 何を教えているのか(2001年度版) | 2001/9/18 | |
| 第13日目 モバイルと私 | 2001/2/ 8 | |
| 第12日目 雪が降る... | 2001/1/17 | |
| 第11日目 新しいパソコンと私 | 2001/1/13 | |
| 第10日目 新年の私 | 2001/1/6 | |
| 2000年 | ||
| 第9日目 沖縄と私 | 2000/11/8 | |
| 第8日目 この頃の私 | 2000/10/22 | |
| 第7日目 なぜこんなことをしているのか | ||
| 第6日目 何を趣味にしているのか(続き) | ||
| 第5日目 何を趣味にしているのか | ||
| 第4日目 どんな学生だったのか(続き) | ||
| 第3日目 どんな学生だったのか | ||
| 第2日目 どこから来たのか | ||
| 第1日目 何を教えているのか | 2000年度版 |

![]() 「えっと、大学で英語の先生をされているんでしたよね?」
「えっと、大学で英語の先生をされているんでしたよね?」
![]() 「そうです。」
「そうです。」
![]() 「どちらの大学ですか?」
「どちらの大学ですか?」
![]() 「名古屋学院大学です。」
「名古屋学院大学です。」
![]() 「瀬戸の方にある大学ですか?だいぶ不便なところにあると...」
「瀬戸の方にある大学ですか?だいぶ不便なところにあると...」
![]() 「ええ、まあそうですね。大学でバスはかなり本数を出していますし、学生用の駐車場もだいぶ広く確保していますけど。」
「ええ、まあそうですね。大学でバスはかなり本数を出していますし、学生用の駐車場もだいぶ広く確保していますけど。」
![]() 「いつからお勤めですか?」
「いつからお勤めですか?」
![]() 「1989年4月に外国語学部が発足して、そのときに専任講師として着任しました。もう10年過ぎちゃいましたね。それ以前に4年間、ここに非常勤講師で来てましたけど、専任の教員になったのは1989年4月です。」
「1989年4月に外国語学部が発足して、そのときに専任講師として着任しました。もう10年過ぎちゃいましたね。それ以前に4年間、ここに非常勤講師で来てましたけど、専任の教員になったのは1989年4月です。」
![]() 「そのころは大学の様子はどんなでしたか?」
「そのころは大学の様子はどんなでしたか?」
![]() 「外国語学部ができたときにはですね、もう第2研究棟はもちろん完成していましたし、現在の希望館も完成していましたから、現在の姿に近かったですよ。もっとも第2食堂ができたのは1年後でしたけどね。ただですね、非常勤講師として一番最初に大学に来たときに、清水先生(現外国語学部長)から、「尾張瀬戸の駅で名学大行きのバスに乗って終点で降りればいいですよ。20分くらいですから」と言われて、バスに乗ったんですけど、瀬戸の町を通りすぎてだんだん山の方に入っていくと不安になってきて、上品野を過ぎて最後のアプローチにかかったときには、もう、本当にこの先に大学があるんだろうかと思いました。その頃は中品野のカレッジハイツとかありませんし、桑下から大学の方にはなにもありませんでしたしね。」
「外国語学部ができたときにはですね、もう第2研究棟はもちろん完成していましたし、現在の希望館も完成していましたから、現在の姿に近かったですよ。もっとも第2食堂ができたのは1年後でしたけどね。ただですね、非常勤講師として一番最初に大学に来たときに、清水先生(現外国語学部長)から、「尾張瀬戸の駅で名学大行きのバスに乗って終点で降りればいいですよ。20分くらいですから」と言われて、バスに乗ったんですけど、瀬戸の町を通りすぎてだんだん山の方に入っていくと不安になってきて、上品野を過ぎて最後のアプローチにかかったときには、もう、本当にこの先に大学があるんだろうかと思いました。その頃は中品野のカレッジハイツとかありませんし、桑下から大学の方にはなにもありませんでしたしね。」
![]() 「で、非常勤講師で英語を教えていたわけですか?」
「で、非常勤講師で英語を教えていたわけですか?」
![]() 「ええ、当時は経済学部しかありませんでしたので、今で言う共通教育の英語をやっていました。LL教室で教えることが多かったです。教材も名古屋学院大学で編集したものを使ったりしておもしろかったですよ。」
「ええ、当時は経済学部しかありませんでしたので、今で言う共通教育の英語をやっていました。LL教室で教えることが多かったです。教材も名古屋学院大学で編集したものを使ったりしておもしろかったですよ。」
![]() 「英語っていっても、いろいろありますが、専門はどのような分野なのですか?」
「英語っていっても、いろいろありますが、専門はどのような分野なのですか?」
![]() 「英語教育学です。どうやって人間は外国語としての英語を習得しているのか、とか、どのような制度で教えられているのか、とか、そんなことに関わる領域ですね。」
「英語教育学です。どうやって人間は外国語としての英語を習得しているのか、とか、どのような制度で教えられているのか、とか、そんなことに関わる領域ですね。」
![]() 「では、大学の授業ではどんな科目を教えていらっしゃるのでしょうか?」
「では、大学の授業ではどんな科目を教えていらっしゃるのでしょうか?」
![]() 「英語教育学ということで、教職課程を担当していますので、まず、「英語科教育法」があります。それから教職課程ということで、「教育実習」とか「教育実習指導」という授業があります。「教育実習」というのは大学での科目名ですが、実際には学生は出身校などに出かけて教育実習をさせてもらうんですが、そのための準備とか、実習校訪問の手配とか、実際に成績が実習校から送られてきてからの処理などを担当しています。「教育実習指導」というのは、教育実習に行く前と行った後で大学の授業として教育実習で何をどのようにするか、ということを扱う授業です。」
「英語教育学ということで、教職課程を担当していますので、まず、「英語科教育法」があります。それから教職課程ということで、「教育実習」とか「教育実習指導」という授業があります。「教育実習」というのは大学での科目名ですが、実際には学生は出身校などに出かけて教育実習をさせてもらうんですが、そのための準備とか、実習校訪問の手配とか、実際に成績が実習校から送られてきてからの処理などを担当しています。「教育実習指導」というのは、教育実習に行く前と行った後で大学の授業として教育実習で何をどのようにするか、ということを扱う授業です。」
![]() 「CALラボの授業もやっていますよね?」
「CALラボの授業もやっていますよね?」
![]() 「そうです。コンピュータとかネットワークを利用して外国語を教えるということも研究テーマの一つです。名古屋学院大学のCALラボは外国語学部が開学部する1年前にできたのですが、これを外国語学部では英米語学科の必修科目で利用してきたわけです。」
「そうです。コンピュータとかネットワークを利用して外国語を教えるということも研究テーマの一つです。名古屋学院大学のCALラボは外国語学部が開学部する1年前にできたのですが、これを外国語学部では英米語学科の必修科目で利用してきたわけです。」
![]() 「やっていてどうですか?」
「やっていてどうですか?」
![]() 「操作方法を覚えたり、授業の進め方を考えたりするときには、普通の授業と違いますから少し面倒ですね。だけど、普通の授業でできないことをやるということで、研究テーマとしてもおもしろいですが、それ以上に授業をやるのも楽しいです。それに、学生がけっこうおもしろがってくれるというのも、教員としてやりがいがあります。」
「操作方法を覚えたり、授業の進め方を考えたりするときには、普通の授業と違いますから少し面倒ですね。だけど、普通の授業でできないことをやるということで、研究テーマとしてもおもしろいですが、それ以上に授業をやるのも楽しいです。それに、学生がけっこうおもしろがってくれるというのも、教員としてやりがいがあります。」
![]() 「他の授業ではどんなものを?」
「他の授業ではどんなものを?」
![]() 「今年(2000年度)は「英語特講2c」を担当しています。これはTOEFL対策の授業ですが、授業でLongmanのテキストを順番にやっていくというものです。テスト&レクチャー形式で、最初の講義の時にスケジュールを渡しておいて、授業ではまずその日の範囲のテストをします。それからその内容を答え合わせをしながら説明するというやり方です。」
「今年(2000年度)は「英語特講2c」を担当しています。これはTOEFL対策の授業ですが、授業でLongmanのテキストを順番にやっていくというものです。テスト&レクチャー形式で、最初の講義の時にスケジュールを渡しておいて、授業ではまずその日の範囲のテストをします。それからその内容を答え合わせをしながら説明するというやり方です。」
![]() 「一年生全員を相手にしている授業もあるんですよね?」
「一年生全員を相手にしている授業もあるんですよね?」
![]() 「それは英語演習111/112のことです。英語検定2級対策の授業です。英語検定の2級に合格すれば授業を受けなくても単位が認定されます。」
「それは英語演習111/112のことです。英語検定2級対策の授業です。英語検定の2級に合格すれば授業を受けなくても単位が認定されます。」
![]() 「一年生は全部で200人を超えていると思いますが、どうやって授業をしているんですか?」
「一年生は全部で200人を超えていると思いますが、どうやって授業をしているんですか?」
「授業の前半で練習問題を約40分くらいかけてやります。これはマークシートに答えを記入してもらいます。次に、マークシートを集めて、その日の問題の答えと解説を配ります。そこで、学生に自己採点をしてもらうわけです。本当は、ここでその日のマークシートを採点してその結果をフィードバックしたいのですが、それは時間的に無理なので、前の週の結果をもとにして説明します。前の週の練習問題のうち、正答率が低い方から、残り時間をだいたい予想して、リストアップした問題を説明するわけです。」
![]() 「毎週、マークシートは採点しているんですか?」
「毎週、マークシートは採点しているんですか?」
![]() 「まあ、こういう授業のやり方をしていますので、毎週やって結果をまとめて、次の週で説明する問題を選んで、プリントにして印刷する、という手順を繰り返しています。」
「まあ、こういう授業のやり方をしていますので、毎週やって結果をまとめて、次の週で説明する問題を選んで、プリントにして印刷する、という手順を繰り返しています。」
![]() 「ところで、大学院の授業も担当してますよね?」
「ところで、大学院の授業も担当してますよね?」
![]() 「大学院は、「英語教育方法論」という授業を担当しています。今のところ、栄サテライトではなくて瀬戸本校の方でやっています。」
「大学院は、「英語教育方法論」という授業を担当しています。今のところ、栄サテライトではなくて瀬戸本校の方でやっています。」
![]() 「これはどんな内容なんですか?」
「これはどんな内容なんですか?」
![]() 「英語教育学の基本的な文献を輪読する、というやり方です。担当者を決めておいて、その日の担当者が、おおよその内容のまとめと自分なりのコメントをして、それについて学生と教員とで質疑応答をするという、大学院の授業としてはいちばんオーソドックスなやり方でしょうね。ちょっと単調ではないかとも思うのですが、やはり、基本文献を読んでいないとどうにもならない、ということがありますから、敢えてこのようなやり方にしています。」
「英語教育学の基本的な文献を輪読する、というやり方です。担当者を決めておいて、その日の担当者が、おおよその内容のまとめと自分なりのコメントをして、それについて学生と教員とで質疑応答をするという、大学院の授業としてはいちばんオーソドックスなやり方でしょうね。ちょっと単調ではないかとも思うのですが、やはり、基本文献を読んでいないとどうにもならない、ということがありますから、敢えてこのようなやり方にしています。」
![]() 「ちょっと気がついたんですが、担当している授業のコマ数が多くないですか?」
「ちょっと気がついたんですが、担当している授業のコマ数が多くないですか?」
![]() 「別に、ちょっと気がついてくれなくても、多いですよ。「教育実習」と「教育実習事前事後指導」を別にしても、7コマ担当してますから。合計で8.5コマです。その他に、単位が出ないけどやっているという、「教育問題特別研究」という授業もありますからね。これは教職課程の4人の教員が順番に担当している科目で、主に、教員採用試験対策の授業です。」
「別に、ちょっと気がついてくれなくても、多いですよ。「教育実習」と「教育実習事前事後指導」を別にしても、7コマ担当してますから。合計で8.5コマです。その他に、単位が出ないけどやっているという、「教育問題特別研究」という授業もありますからね。これは教職課程の4人の教員が順番に担当している科目で、主に、教員採用試験対策の授業です。」
![]() 「大丈夫ですか?」
「大丈夫ですか?」
![]() 「来年度(2001年度)は通信制大学院(現在文部省申請中)の担当が回ってきそうなので、もう一つくらいは上積みされるでしょうね。」
「来年度(2001年度)は通信制大学院(現在文部省申請中)の担当が回ってきそうなので、もう一つくらいは上積みされるでしょうね。」
![]() 「.....」
「.....」
![]() 「まあ、「毒を喰わば皿まで」とか言いますし。ただ、「そこまでやっているならもう一コマくらい同じことじゃない」と言って来た先生もいらっしゃいましたけど(名前を挙げたいけど、某前教務委員です)、その、「あと一歩踏み出したらそこが崖だった、」ということがありますので、気をつけようと思っています。ハイ。」
「まあ、「毒を喰わば皿まで」とか言いますし。ただ、「そこまでやっているならもう一コマくらい同じことじゃない」と言って来た先生もいらっしゃいましたけど(名前を挙げたいけど、某前教務委員です)、その、「あと一歩踏み出したらそこが崖だった、」ということがありますので、気をつけようと思っています。ハイ。」
![]() 「.....」
「.....」
このページのトップへ戻る![]()
自宅のページへ戻る![]()
ホームページのトップへ戻る![]()
